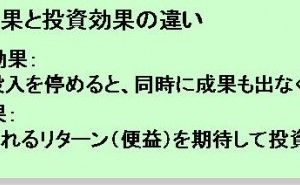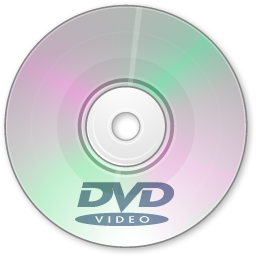人口減少による人手不足、既存製品のコモディティ化、新技術の導入などに対応していくために、企業が自社の開発力を強化する必要性が高まっています。そのために開発組織の見直しや使用ツールの変更など様々な取組みが行われていますが、特に重要なのが開発力への影響が大きい技術人材の力量を向上させるための教育です。
これまでも独自の技術人材育成のカリキュラムを設けている企業もありますが、教育プログラムを設けずに業務を通した育成を中心としてきた企業では技術人材を育成していくシステムそのものを構築しくことが必要となります。その際、人材育成は成果予測の難しい長期間の投資活動であり、どのように進めたらいいかが分らないために具体的な取り組みに至らないことも多いのではないでしょうか。
ここでは、そうした背景を踏まえて、効率的に成果を上げることに焦点をあてた技術人材育成の進め方について解説しています。今回は、前回の技術人材育成の進め方(その2)計画と実施2に続けて、解説します。
◆関連解説記事:開発効率を上げるには【連載記事紹介】開発コスト低下とスピード向上
1. 人材育成における注意点
組織内の意思伝達が十分でなく、育成目的が十分に関係者に理解されていない場合は、次のような課題が発生して十分な成果が得られないことがあります。計画作成や育成活動の際には、これらの点にご注意ください。
(1) 組織における教育の位置付け
組織のマネジメント側が、自組織のミッションを「業務上の成果を出すこと」と捉え、教育に十分なリソースを割り当てない場合があります。このような状況を回避するため、経営トップから「組織・人材をつくることが、組織ミッションの一つであり、マネジメントはその成果に対する責任がある」という明確なガイドラインを出す必要があります。
(2) 人事評価との関係
通常、教育を受けるメンバーは自身のスキル向上につながるために教育を受けることにポジティブですが、組織の意図を汲み違えて「教育受講が、職位が上がる条件」と考え、沢山の教育を受ければいいものと勘違いする場合があります。こうした状況を回避するために、教育の結果を生かした業務での「成果」を評価するという考え方を浸透させておく必要があります。
(3) 業務と自己啓発
メンバーに教育を行う場合、(特に通信教育など自宅で行うもののようなものは)それが業務なのか、自己啓発なのかが問題になることが多々あります。この点に関して「組織からの要請で行ったものが業務」「個人のスキル向上も業務に役立つので一定の補助をおこなう」など、明確なルールを定めておくことが必要です。
(4) 方向性の誤り
教育の目的がメンバーに十分に伝わらなかった場合、例えば下記のように違う方向に育成が進み、結果として十分な成果が得られない場合があります。これを回避するためには、ある程度現場に入り込んだ管理、定期的な進捗確認などを行う必要があります。
- トップは新技術への移行を求めているのに、現場は既存製品開発力増強の教育をする
- 教育される側が、個人のスキルアップのみを目的とする
- 学習範囲を定めず、不必要な学習に時間を使ってしまう
(5) 技術伝承の副次的影響
組織のノウハウや蓄積した技術を伝承する場合、以下のような副次的な影響が生じます。これを回避するためには、伝承する内容を十分に吟味することが必要になります。
- 伝承内容に沿って設計を行うため、開発スピードが大幅に改善されるが
- 伝承されていない開発・設計を行う力が失われていく
- 伝承内容に不備があると、それがそれ以降の全ての製品に適用されてしまう。
3. 全体の見える化で組織力強化へ
技術人材育成は、対象の人数やレベル、教育手段の多様さなどを考えると組合わせが多く、実際に計...