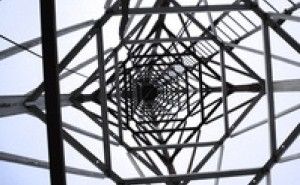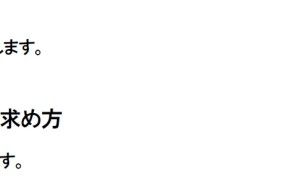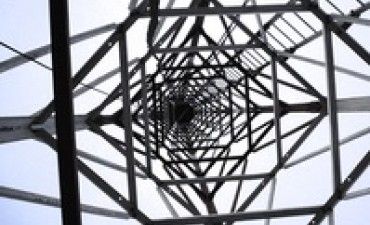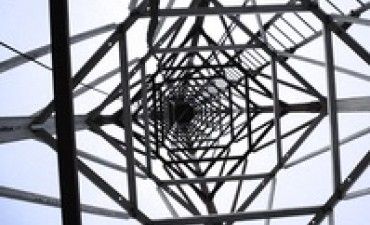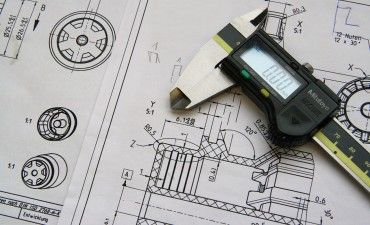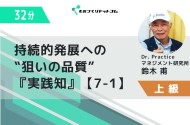1.品質工学の狙いは高品質と低価格化の両立
工場の出荷品質を向上させただけでは、もはや社会は満足してくれなくなりました。製品が破棄されるまでのすべての期間、さらには破棄された後、地球環境に対する影響まで含めた広範囲の品質が要求されています。
また品質に対する要求以外に、忘れてはならない項目があります。価格です。産業革命以来、大量消費社会はコストパフォーマンスを追求し続けてきました。「同じ快適な生活ができるなら、価格は少しでも安い方がいい」「より高い品質の製品を、できるだけ低価格で供給しなければならない」。消費社会の欲求は限りがありません。
いま、モノづくりは大きな転換を期待されています。高品質への要求と更なる低価格化の要求。この一見矛盾する要求を達成しなければ、低賃金国の追い上げに対処できません。モノづくりに携わる技術者にとっては、大変に困難な時代を迎えているのです。
品質工学では、高品質と低価格化を両立させる考え方を提案しています。そのポイントは「品質はコストダウンの手段」ということです。なぜならば、品質向上を通じてでしか真のコストダウンはできないからです。品質を向上させないでコストダウンをすれば、必ず問題を発生させます。コストを上昇させずに品質を改善する技術を開発しない限り、真に競争力のあるコストダウンはできません。
真のコストダウンを行うには、技術と製品開発に携わる人材の育成が不可欠です。今後のモノづくりはどうあるべきか、それを支える人材の育成をどうするか。考え方の変革つまりパラダイムシフトの視点で、品質工学を理解する必要があるのです。
2.品質工学は、品質管理の限界を超える
「品質管理をきちんと行い、万全の検査を行って出荷したはず。それなのに、市場で不具合が発生しリコールをしなければならない。なぜだろう」と悩んでいる製造現場が多くみられます。「日本のモノづくり力はそんなに落ちたのか」。周囲からは、そんな声も聞かれるようになりました。
しかし心配は無用です。モノづくりの技術力が落ちたのではありません。いままで成功してきた品質管理の方法に限界が見えてきただけなのです。すでに先進企業では、新しい状況に対処しようとして、限界を超える新しい方法論を使って走り出しています。その新しい方法論とは品質工学です。品質工学が従来の品質管理で見つからなかった問題点を明らかにし、それを未然に防止する方法を提供できるからです。
QC サークルや「なぜなぜ分析」に代表される日本の品質管理手法の優秀さは、世界中で有名です。モノづくりの現場での「カイゼン」などの日本語は、いまや世界共通語になっています。日本に追い付こうとしている国々は「日本に学べ!」を合言葉に日夜努力しているのです。そのように大成功した品質管理の手法ですが、かなり以前から限界が見えていました。その現れのひとつがリコールの多発です。リコールを引き起こす不具合問題が、従来の品質管理の手法では見つけられないのです。万全の検査を行い、100%の合格品を出荷したはずなのに市場で不具合が起きるのですから、品質管理を従来以上に厳しくしても、もはや対策にならないのは明らかでしょう。
では、どうすればいいのでしょうか。品質工学は、この限界を打ち破る考え方として注目されています。単なる最適化実験の手法ではありません。モノづくりの根幹を変革する提案なのです。だから先進企業が意欲的に取り組んでいるのです。
3.品質工学は品質管理と何が違うか
品質工学と品質管理とは名称が似ているので、同じものだと誤解している人も多いようです。まったく違うのです。ここで違いをはっきりさせておきましょう。
QCと呼ばれる従来型の品質管理は、なぜなぜ分析やQC7 つ道具や問題解決手法などが有名で、主に製造部門を対象とした管理...