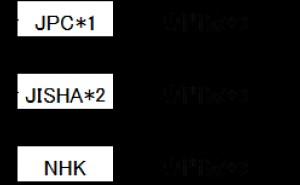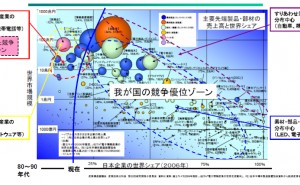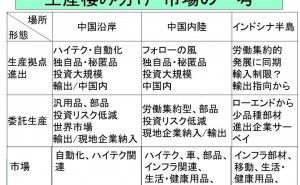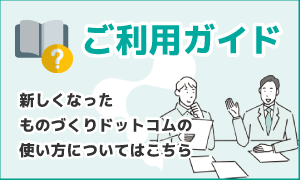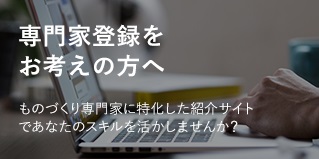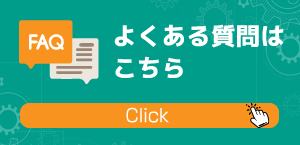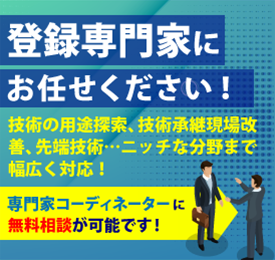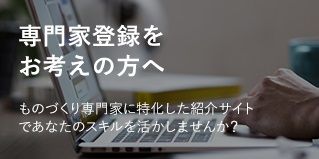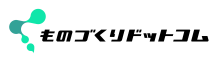前回のその2に続いて解説します。第3回はベネズエラの続きです。当時、ベネズエラは石油資源で潤っていて、このプロジェクトも石油資源から得られる資金をもう一つの国家資源である鉄鋼の発展に振り向ける国家プロジェクトでした。
ラテンの国の人々は、だいたい生活を楽しむために働くのであって、物事はすべて、そしていつまでたってもアスタ・マニャーナ(明日また、明日にならなければ分らない)で、仕事に生きがいを持つという日本とはまったく逆である。そして制度的にはベネズエラは先進国で、完全週休2日制、おまけに1年に1ヶ月は休暇をとることが義務付けられている。人手不足でどんなに忙しくとも、またどんなに計画より遅れていようと、幹部クラスをはじめ次々と交代で休暇をとってしまうのである。
このような文化・社会構造をもっているところでは、現地に派遣されたものが日本の何倍も努力をし、何倍もの時間を使っても、あがる成果は何分の一かでしかない。このようは状況下では、戦線を広げたままでは何時になっても成果はあがらない。
この5年のプロジェクトは2年+2年+1年(作業長の場合は諸般の事情から8ヵ月ごと)とメンバーを交替して対応したわけだが、その度ごとにわれわれの体制の見直しを行い、最終的に重点部門のみに絞り込んで精力的に対応することによって成果を上げ、日本の技術指導のやり方の良さが認められたのである。
振り返ってみると、初期にはいろいろとすれ違いが生じていたが、「契約の時にノルマ・ペナルティ方式を絶対受け付けなかったこと」「先方の要求を聞き、可能な限り手を打ってきたこと」そしてその間に「先方の文化・社会構造を理解して、それにあった戦略と戦術をとったこと、すなわち重点部門にしぼり、現場に入り込んで陣頭指揮をとって仕事を進めたこと」、これらが成功の大きな要因になった。先方社長も「現場に入り込んで陣頭指揮をとった指導」に感謝の意を表した。
それにしてもこれらを可能にしたのは、やはり当方の初期のリーダーの対応力と途中での先方のトップの人事異動に負うところがが大きい。このような大きなプロジェクトでは、違った製鉄所あるいは系列会社まで含めた寄合所帯となり、お互いの気心が知れないうちに仕事の面でも生活の面でも、皆が大きなカルチャーショックを受け、イライラし出す。それに先方は日本の専門家が来たのだから翌日からでも操業成績はどんどんあがるものと期待しており、一方日本のやり方は試行錯誤の積み重ねですこしずつ良くしていくというものであるから、大変なチグハグが生じる。したがって初期のリーダーは、寄り合い所帯のメンバーを統率する力と、先方を理解しかつ説得する力と、本社に現地の実態をうまく説明し説得する力をもっていることが必要である。
また先方のトップがずっと短期成果主義で少しもこちらのいうことを聞こうとせず、部下を指導する力(気)もなかったとすると、話は全く進まなくなる。やはり途中でこちらのいうことに耳を傾け、かつ部下を説得しやらせる力を持った人にめぐり合ったことが大きなカギである。
実際、当初先方トップ(製鉄所長)は、レバノン(昔フェ二キュアと呼ばれ商業に長けたユダヤと並ぶ優秀な民族)系でガンガン攻めてきたが、途中で温厚で聞く耳を持ったトップに替ったことで新たな展開が可能になった。写真1...



 写真1.男だけの社長主催サヨナラパーティー
写真1.男だけの社長主催サヨナラパーティー