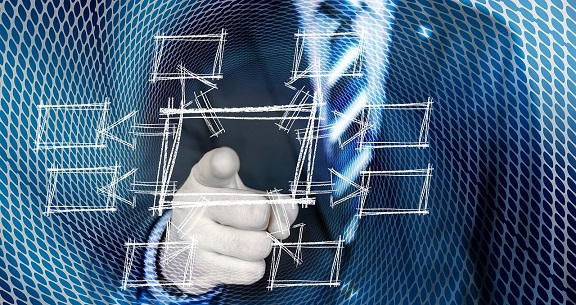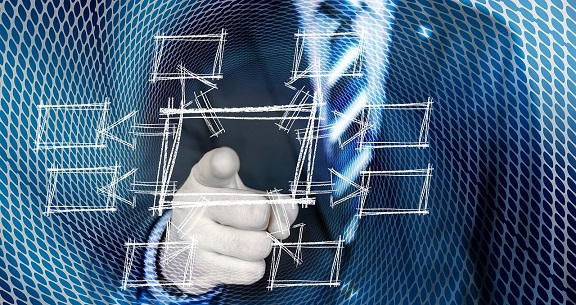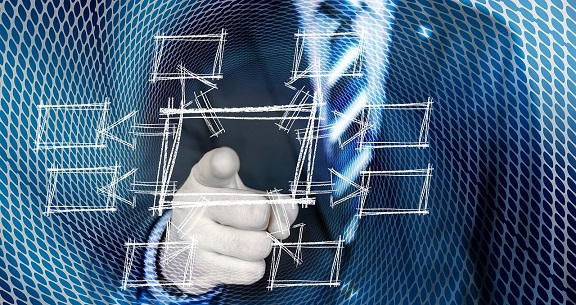1. 管理監督者の現場入り
皆さんの会社では管理職の方がいて、監督者の方が現場を管理されていることだと思います。この管理者と監督者を合わせて管理監督者と呼ぶことが多いようです。そこで今回は、管理監督者への仕事の任せ方について考えていきたいと思います。
会社は組織ですから、それぞれの職位の方が託された業務を実行することが求められます。ここで確認しておきたいことがあります。それが管理監督者の仕事の仕方なのです。ここを間違えると会社の業務効率が低下してしまいます。意識的に管理監督者の実施している仕事を見直していくことが求められます。
大きな課題があります。それはまだ多くの会社で管理監督者が自分の役割を理解していないことです。または、誤解しているといった方がふさわしいかもしれません。
では、どのような誤解なのでしょうか。それはずばり「現場に入り込んで現場の実業務をサポートすること」が管理監督者の業務であるという誤解です。日本では現場重視です。製造業でも物流業でも、現業の仕事をとても大切にします。これは間違った考え方ではありません。
なぜなら、現場あっての会社だからです。しかし、だからといって、現場の仕事に管理監督者が入るということは明らかに間違っています。日本では現業とスタッフの壁が低く、スタッフが現場に入り込むことが昔から当然のように行われており、それに対して違和感を抱かない雰囲気がありました。現場は生き物ですから、次のようにいろいろなことが起きます。
・作業者の突発的な欠勤
・得意先からの緊急オーダー
・突発の品質不良発生
このようなことが日常茶飯事で起きています。ポイントはこのような事象に対して管理監督者がどのように対応するのか、ということです。たしかに1年で管理監督者が現場応援を1回も行わないということは現時点では難しいかもしれません。
でも、なぜ高い給料をもらう管理監督者がいるのでしょうか。そこを考えていただきたいのです。どこの産業、どこの会社でもこのような突発業務は起きます。物流だけということはありえません。管理監督者はこのような突発業務も想定し、現場マネジメントをすることが課されています。本来ならばこの管理がしっかりとされているのであれば、それほど頻繁に現場が混乱することはあり得ないのです。
2. 労働生産性の国際比較
日本では管理者も監督者も現場を応援すべきだ、皆で現場作業を行うことが現場のモチベーション向上につながり、それが会社の発展にもつながる、昔からこのような言われ方をしてきました。
このような考え方は欧米では考えられません。なぜなら職種が現業と事務スタッフでは異なるからです。まして管理者が一作業者として働くことなどあり得ないのです。最近少なくはなってきましたが、日本ではまだスタッフや管理監督者の現場入りが行われています。これによって「本業」を行う時間が失われます。管理監督者が行うべき業務が滞ります。結果的に会社は現場の実態が数字で見えなくなり、感覚的な運営に走らざるを得なくなります。
皆さんは日本の労働生産性の国際水準をご存知でしょうか。日本生産性本部の調査「就業者 1 人当たり労働生産性の国際比較」によると、2017年の日本のポジションはOECD35か国中21位です。先進7か国では常時最下位です。強いといわれ続けてきた製造業ですら14位なのです。製造業はかつては1位、2位を争う時期もありましたが、今や見る影もありません。
この要因の一つが働く人一人ひとりが与えられた仕事を100%やりきっていないことが考えられます。管理監督者が一つの例です。管理監督の職位にいる方が現場入りすれば、管理業務ができなくなるだけでなく、現場の一人当たりの労働生産性を落としてしまう可能性があります。なぜなら現場作業員が本来できる力を発揮しなくても、管理監督者が「工数」になってくれるために目標出来高が出てしまうからなのです。
では管理監督者が現場入りする真の要因はなんでしょうか。これは表面上は自分の管理能力不足で突発事象に現場が対応できないためだと想定できます。しかし本音は、管理監督者の「逃げ」だと思います。本来なら現場作業者に「やらせなければならない」のです。でも、それができない。現場入りすることは管理業務を放棄し、簡単な仕事に逃げていることに他なりません。もし管理監督者からもし自分が入らなかったら出荷が止まると脅されたとしましょう。
会社の経営者はこのような「言い訳」を言わせないように、まず言い分を聞いてみて下さい。たとえば工数が1人足りないという言い分に対しては一時的に1人補充し、管理監督者の「言い訳」の道をふさぎましょう。もしこれで正常に戻らなかったとしたら・・・・。もうお分かりですね。経営者の方は管理監督者の育成が不足していたのか、人選ミスだったのかということになります。
3. コーチングを学ばせる
管理監督者の方は部下の方に正しい仕事をしてもらうように努力する必要があります。そのためには作業をきちんと標準化し、その通りに教え、やらせてみることです。部下を思い通りに動かす難しさを感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。特に長年その現場で仕事をしてきた年上の部下などに対しては、対応に苦労することがあるかもしれません。長年ずっと同じ仕事の仕方をしてきた人にとって、仕事のやり方を変えることには抵抗感があることでしょう。
しかし、管理監督者の方はここでひるんでいてはいけません。会社の方針が変わったり、品質不良が多発したりして仕事を追加しなければならな...