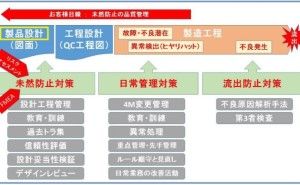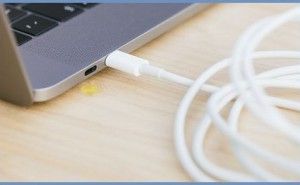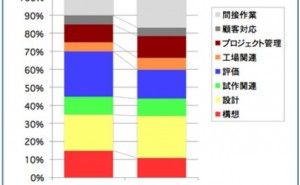【製品設計:ミス防止対策 連載目次】

設計品質を確保するのに重要な
過去トラブルの有効利用について解説します。
1. 過去のトラブル、フィードバックの問題点
どの会社でも過去トラブルのデータを収集して有効利用しようと考えています。しかしながら、次の3点の管理上の問題が見られます。
・「過去トラ」を登録・管理するための仕組みが不明確
・「過去トラ」の件数は増加し続ける
・「過去トラ」の登録内容がメンテナンスされていない
また、それを利用する設計者側の問題としては、次の5点です。
・「過去トラ」の利用方法が開発現場任せになっている
・ 利用される「過去トラ」は身近なものに限られている
・「過去トラ」が利用されないこともある
・「過去トラ」の利用効果を確認していない
・「過去トラ」の利用効果がフィードバックされるのはその部署のみ
但し、これらは設計者個人の問題と言うよりも開発設計部門の仕組みとして、それぞれの企業の事情に応じた過去トラ利用システムを次の点を考慮して構築する必要があります。
・「過去トラ」の情報共有の場を構築する
・蓄積した「過去トラ」を適切に分類し、体系化する
・効果を客観的に判断するため、活用状況や品質を定量化し計測する
・増え続ける「過去トラ」の改廃や再発したときの既存情報へのフィード
皆様の開発部門ではどのように過去トラを活用しているでしょうか、各設計者の頭の中にあるので、それを聞き出して設計しているという会社も多いのではないでしょうか。
2. 過去トラの宝庫、大部屋設計フロアー
昔は、設計室というか、仕切りもない設計フロアーには何百人という設計者が、製品設計を行っていました。ベテランから新人まで、機構設計、電子回路設計、ファームウエア設計などあらゆる設計を行っており、何か分からない事があると、「あの人なら以前このような製品でこのような機能を実現しているので、効くと言いよ」と教えられ、聞きに行った...
 設計品質を確保するのに重要な過去トラブルの有効利用について解説します。
設計品質を確保するのに重要な過去トラブルの有効利用について解説します。