【製品設計:ミス防止対策 連載目次】
② 具体設計に着手する
③ 技術的手段(方式)の妥当性を確認する
④ 実際に試作検証して設計通りのものか確認する
⑤ 最終のアウトプットとして、設計図面をリリースする
1.標準化の意味
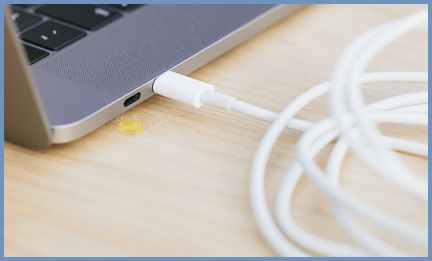 「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。
「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。TOP

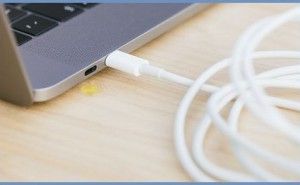
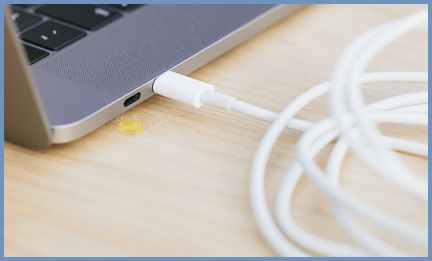 「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。
「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。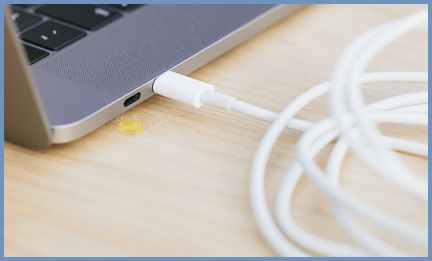 「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。
「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。続きを読むには・・・
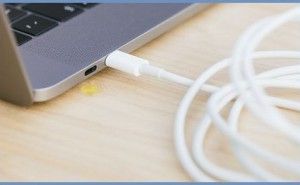
現在記事
イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...
イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...
2020年、新型コロナウイルスの影響下、このような時期なのですが、中長期の技術戦略を立てたいという会社からの問い合わせを頂いています...
2020年、新型コロナウイルスの影響下、このような時期なのですが、中長期の技術戦略を立てたいという会社からの問い合わせを頂いています...
【製品設計:ミス防止対策 連載目次】 1. お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」 2. 過去のトラブル、フィー...
【製品設計:ミス防止対策 連載目次】 1. お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」 2. 過去のトラブル、フィー...
1. 研究開発テーマの創出 未来の事業や商品につながる新たなテーマの創出は、研究開発における最重要課題の一つです。とりわけ、ものづくり...
1. 研究開発テーマの創出 未来の事業や商品につながる新たなテーマの創出は、研究開発における最重要課題の一つです。とりわけ、ものづくり...
前回からの続きです。前回ではまず製品開発工程の価値(物と情報)の流れ図を作り、工程上の問題点...
前回からの続きです。前回ではまず製品開発工程の価値(物と情報)の流れ図を作り、工程上の問題点...
1. 国際財務報告基準とは 国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards)...
1. 国際財務報告基準とは 国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards)...
合同会社高崎ものづくり技術研究所
製造業に従事して50年、新製品開発設計から製造技術、品質管理、海外生産まで、あらゆる業務に従事した経験を基に、現場目線で業務改革・経営改革・意識改革支援に...
開催日: 2026-03-18
開催日: 2026-03-26
開催日: 2026-05-19
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



