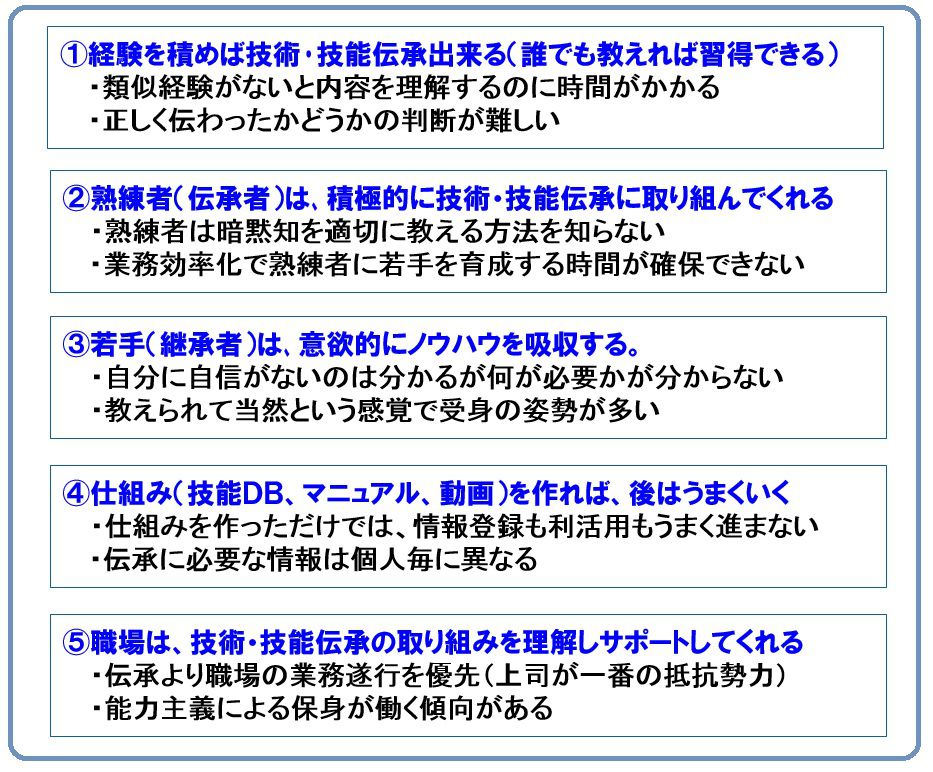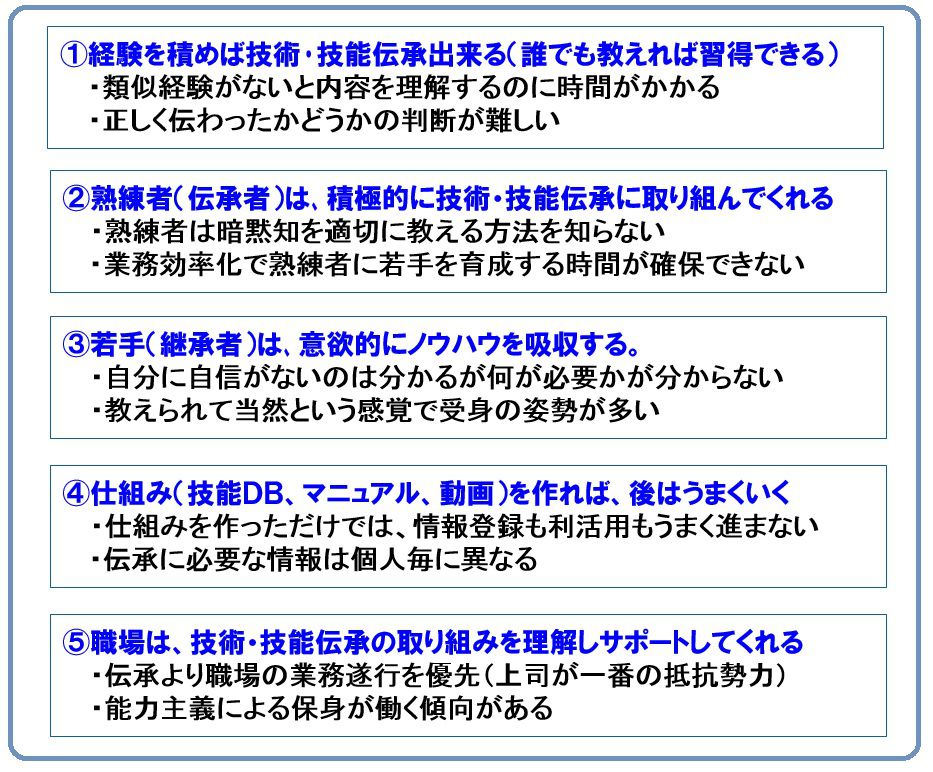1.技術・技能伝承が進まない
グローバル化の進展により、日本を取り巻く環境は大きく変化しています。新興国の台頭や国際間競争の激化など、産業構造や就業構造そのものが変化していく現状では、その事に対応したモノづくりの自己変革が求められています。そして、経営資源が脆弱な中小企業、古い技術やシステムなどレガシー資産を抱える基幹産業や製造業、また構造的な問題を抱える業界などは、技術・技能伝承が進展していないため、モノづくりの自己変革が遅れて、このことが深刻な問題となっています。
(1)今なぜ技術・技能伝承なのか
我が国は、団塊世代の高年齢化と少子化の進展により、少子高齢化社会を迎え、世界最高水準の高齢化率となっています。内閣府が発表した平成24年度版高齢化白書によれば、今後50年間で生産年齢人口(15~64歳の全人口比率)が半減するという試算もあり、また15歳~29歳迄の若手と30歳~65歳迄の中高年の人員比率が、2010年で1:10と1980年代に比べ倍増しています。つまり、若手1人に対し、技術や技能を伝承する熟練者が10人も存在していることになる。この傾向は今後増々進展することが確実であり、次世代へ残すべき技術・技能を見極める重要性が増しています。
そもそも技術・技能とは、どのようなものでしょうか。我々は、暗黙知の状態にある属人ノウハウを技術と技能に区分しています。技術は、属人ノウハウを文字や数式などで形式知化しやすく、標準化や自動化など全体作業レベルを底上げするものです。また技能は、人間が行う動作や動きで主観的なもので、人間を介在...