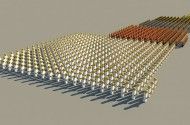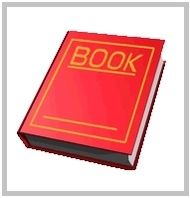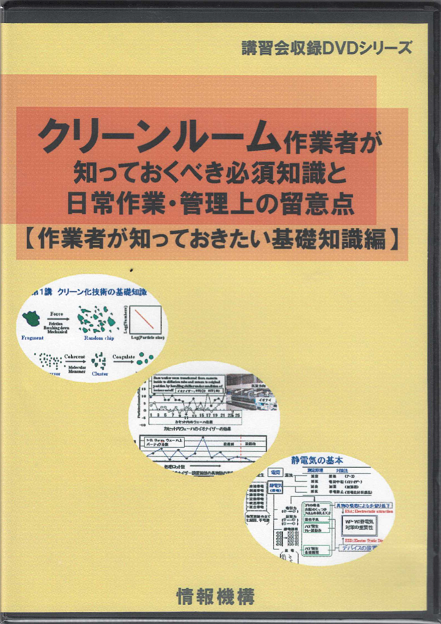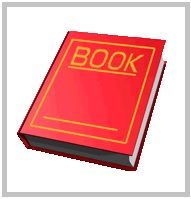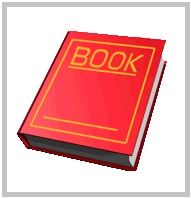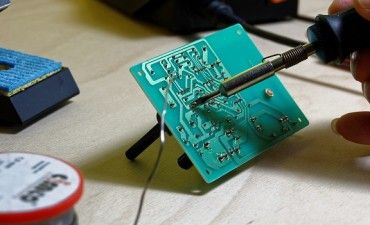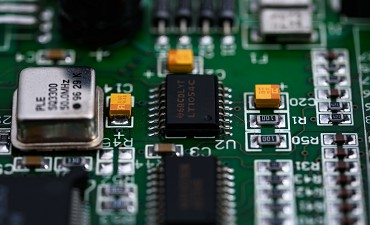「洗浄バリデーション」「マルチパーパス設備洗浄評価基準」コース
【Aコース】 4/23開催 ≫ 高薬理活性物質を扱うマルチパーパス設備での洗浄評価基準と洗浄管理の留意点
【Bコース】 4/25開催 ≫ 洗浄バリデーションにおける
「残留許容値の設定」「ホールドタイム(DHT/CHT/SDT/SHT)の留意点」
「ワーストケースロケーション(WCL)とスワブ数の例」「回収率テストの事例」
日時
Aコース【Live配信受講】 2025年4月23日(水) 13:00~16:30
Aコース【アーカイブ配信受講】 2025年5月12日(月) まで受付(配信期間:5/12~5/23)
Bコース【Live配信受講】 2025年4月25日(金) 10:30~16:30
Bコース【アーカイブ配信受講】 2025年5月14日(水) まで受付(配信期間:5/14~5/27)
※受講可能な形式【Live配信】or【アーカイブ配信】
※Aコース、Bコースそれぞれで「Live配信受講」or「アーカイブ配信受講」の選択が可能です。
その場合「Live配信受講」にてお申込みいただき、申込みフォーム備考欄にて、アーカイブ配信受講のコースをご連絡ください。
※Live配信受講者には、特典として「アーカイブ配信」の閲覧権が付与されます。
セミナープログラム
【Aコース】4/23開催
≫ 高薬理活性物質を扱うマルチパーパス設備での洗浄評価基準と洗浄管理の留意点
セミナー趣旨
本セミナーでは,高薬理活性物質を扱うマルチパーパス設備での洗浄に必要とされる事項について説明する。マルチパーパス設備では,品質確保の観点から交叉汚染防止が必須である。そのための科学的ツールは,改正GMP省令,PIC/S GMP で導入している「健康ベース曝露限界値」(HBEL)である。高薬理活性物質を扱う場合には,HBELに基づく洗浄閾値が極端に小さくなることもあり,対応が必要である。
講座では,ライフサイクルアプローチに基づく洗浄バリデーションの概要,HBELの設定(データが少ない場合,中分子の場合,不活化高分子の場合などへの対応を含む),HBELに基づく洗浄管理基準(製品接触部・製品非接触部・封じ込め機器内の間接製品接触部を含む),目視検査,シミュレーション事例,ハザードレベルの違いによる洗浄管理(洗浄閾値が極端に小さくなる場合への対応など),今後の洗浄バリデーションの流れを説明する。さらに,査察時に話題となる項目(ワーストケースアプローチ,サンプリングポイントの選定,回収率の設定, CHT,変更管理)について取り上げ,対応策をISPE洗浄ガイドなどに基づき説明する。また,付録では,リスクベースでの逸脱管理についての提案,洗浄に関する指摘事例についての解説も含めている。
セミナー講演内容
1.高薬理活性物質を扱うマルチパーパス設備での洗浄に必要とされる対応
1.1 ライフサイクルアプローチに基づく洗浄バリデーション
1.2 洗浄工程でのリスク評価とQRM
1.3 科学的なツールHBELの利用
1.4 専用化要件の検討
1.5 洗浄バリデーションにおける2つの指標の設定
1.6 ハザードレベルの違いによる洗浄管理
2.健康ベース曝露限界値(HBEL)
2.1 概要
2.2 HBELの定義・位置付け・用語
2.3 HBELの計算式
2.4 毒性データが限定されている場合の対処
-TTCの概念による方法
-Control Bandingの下限値から求める方法
-中分子,不活化高分子,洗浄剤などへのデフォルトの利用
2.5 洗浄閾値が小さい場合のツール~プロダクト特定ADEの考え
2.6 HBELを巡る課題
3.HBELに基づく洗浄管理基準
3.1 製品接触部における洗浄管理基準
-洗浄閾値(SRL)の計算式と用語
-洗浄閾値の意味合い~SRLとroutine cleaning limits
-安全マージン
3.2 製品非接触部における洗浄管理基準
3.3 封じ込め機器内の間接製品接触面における洗浄管理基準
3.4 伝統的な洗浄管理基準の取り扱い
4.目視検査
4.1 目視検査の位置付け
4.2 目視で検出できるレベル
4.3 目視検出限界の設定方法論
4.4 目視検出限界をめぐる課題
5.洗浄評価シミュレーション
5.1 シミュレーションの前提条件と計算結果
5.2 ハザードレベルとSRLの数値
5.3 SRLとVRLの関係
5.4 シミュレーションからの知見
6.ハザードレベルに応じた洗浄目標の設定
6.1 安全マージンを考慮した洗浄目標設定
6.2 SRLが比較的に高い場合への対応
6.3 SRLが極端に低い場合への対応
6.4 ケーススタディその1
6.5 ケーススタディその2
6.6 ケーススタディその3
6.7 次製品の使われ方によるSRLの調整
7.今後の洗浄バリデーションの流れ
8.査察時に話題になる事項への対応
8.1 ワーストケースアプローチの根拠
8.2 サンプリングポイントの選定根拠
8.3 サンプリング時の回収率設定
8.4 CHT~バイオバーデン限度値の設定
8.5 変更管理
□質疑応答□
【Bコース】4/25開催
≫ 洗浄バリデーションにおける
「残留許容値の設定」「ホールドタイム(DHT/CHT/SDT/SHT)の留意点」
「ワーストケースロケーション(WCL)とスワブ数の例」「回収率テストの事例」
セミナー趣旨
洗浄バリデーションの残留許容値の設定について、毒性データに基づく健康ベース暴露限界値(HBEL)が要請されている。しかし、HBELの算出は容易でない。また、スワブサンプリングの仕方や回収率テストの手法等、実務者は多くの疑問や問題を抱え試行錯誤を繰り返されているのではないであろうか。本講は、洗浄バリデーションの実務者として知っておくべき基礎知識と、実務者が抱える諸課題について、演者の経験を踏まえつつ一緒に考えていこうという講座である。
セミナー講演内容
1.交叉汚染リスクへの対応が注目されている
1.1 最新GMPが求める医薬品品質システム(PQS)とは
1.2 現実世界には品質リスクマネジメント(QRM)が必要
1.3 汚染管理戦略(CCS)が必要
1.4 交叉汚染対策に関する査察時の指摘ポイントを知る(PIC/S備忘録PI043-1)
2.洗浄対象物に思い込みをしない
2.1 洗浄バリデーションは専用設備でも必要
2.2 原薬供給業者が変われば不純物も変わる
2.3 設備材質からの溶出物・浸出物も要注意
2.4 洗浄剤、微生物も洗浄対象
2.5 乾燥終了までが洗浄バリデーション
2.6 CCSの一環として洗浄バリデーションマスタープランを策定
3.ダーティホールドタイム(DHT)とクリーンホールドタイム(CHT)
3.1 長期間保管後に再洗浄すれば良い?(洗浄対象物が変わっているかも)
3.2 CHTを実機で設定できる?
3.3 ヒトがいれば発塵する
3.4 スモークスタディの要請
3.5 環境モニタリングデータの精度は低い
3.6 床、壁の残留許容値はどう考える?
3.7 分析機器のキャリーオーバーに注意
4.残留許容値の設定
4.1 残留許容値の考え方の歴史
4.2 FourmanとMullin論文が一世を風靡
4.3 0.1%基準、10ppm基準の問題点
4.4 投与量基準から毒性発現量基準へ
4.5 そもそも毒性とは
4.6 ISPEのRisk Mapp(Baseline Guide)の論点とADE
4.7 EMA(欧州医薬品庁)ガイドラインとPDE
4.8 ASTM E3219-20のHBELの計算式
4.9 HBEL(毒性発現量基準)の設定は専門知識が必要
4.10 HBELに関する動向
5.不純物・分解生成物の限度量
5.1 ICH Q3ガイドラインの問題点
5.2 遺伝毒性不純物はどう考えるか
5.3 ICH M7変異原性不純物ガイドライン
5.4 私見によるまとめ
6.微生物(発熱性物質)の残留許容値
7.洗浄剤の残留許容値
7.1 LD50を用いることの議論
7.2 各種洗浄剤、溶剤の紹介
8.洗浄剤と自動洗浄(CIP)、手洗浄(COP)の留意点
8.1 配管のCIPで留意すること
8.2 スプレー装置で留意すること
8.3 Worst case Location
8.4 デッドレグは短く
8.5 COPの留意点
9.サンプリング方法の留意点
9.1 スワブ法の問題点
9.2 サンプリング箇所の設定
9.3 どこからどれ位サンプリングするか
9.4 接薬表面積の算出例
9.5 その他のサンプリング法と問題点
9.6 TOCによる残留確認
9.7 サンプルの安定性に留意(Sampling Delay Time、Sample Holding Time)
10.回収率テスト
10.1 回収率テストの例
10.2 回収率の計算
11.査察時の指摘事例
□質疑応答□
セミナー講師
島 一己 氏
ファルマハイジーンサポート
略歴
1975年 東北大学大学院工学研究科機械工学修士課程修了
1975年 東洋エンジニアリング(株)に入社
2014年 東洋エンジニアリング(株)を退社
2014年5月 ファルマハイジーンサポートを設立。
東洋エンジニアリング(株)に在職中は、長年にわたり、バッチプラントに関係した案件のコンセプトメイキング、研究開発、商品化、洗浄実験、営業支援、実案件での設計、運転などに携わる。特に、マルチパーパスプラント、タンク移動方式、配管切り替え装置XYルータ、洗浄、封じ込めなどの分野に従事。
XYルータでは、化学工学会技術賞を受賞(1988年)。
在職中の特許出願 約120件。
封じ込め関連の技術報文 多数。
著書 封じ込め技術のすべてがわかる本(絶版)
封じ込め技術(森北出版)
主な研究・業務
封じ込め設備に関するコンサルティング
業界での関連活動
ISPE会員
-----
髙木 肇 氏
医薬品GMP教育支援センター代表
略歴
塩野義製薬株式会社にて、経口剤や凍結乾燥注射剤などの工業化検討、無菌製剤製造棟の構築プロジェクト遂行、国内外関連会社への技術指導、無菌製剤棟の製造管理責任者など、製剤開発から工場運営に渡る幅広い任務を実施。
業界での関連活動
台日製薬工業交流セミナー(台湾経済部工業局主催、医薬工業技術発展センター開催)での講演を始めとする台湾企業への技術指導、および国内食品・医薬品・医療器具メーカーへの技術支援を実施。
セミナー受講料
※お申込みと同時にS&T会員登録をさせていただきます(E-mail案内登録とは異なります)。
77,000円 ( E-Mail案内登録価格 73,150円 )
定価:本体70,000円+税7,000円
E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料
2名で77,000円 (2名ともE-Mail案内登録必須/1名あたり定価半額38,500円)
テレワーク応援キャンペーン(1名受講) オンライン配信セミナー受講限定】
1名申込みの場合:受講料( 定価 66,000円/E-Mail案内登録価格 62,700円 )
定価:本体60,000円+税6,000円
E-Mail案内登録価格:本体57,000円+税5,700円
※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。
※他の割引は併用できません。
▼単コースでの受講を希望の方は、備考欄にご希望コースを記載ください▼
【Aコースのみ受講】
定価 49,500円/E-Mail案内登録価格 46,970円
2名で49,500円(E-Mail案内登録価格 1名あたり24,750円)
テレワーク応援価格39,600円(E-Mail案内登録価格 37,840円)
【Bコースのみ受講】
定価 55,000円/E-Mail案内登録価格 52,250円
2名で55,000円(E-Mail案内登録価格 1名あたり27,500円)
テレワーク応援価格44,000円(E-Mail案内登録価格 42,020円)
<1名分無料適用条件>
※2名様ともE-mail案内登録が必須です。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価半額で追加受講できます。
※請求書(PDFデータ)は、代表者にE-mailで送信いたします。
※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。
(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※他の割引は併用できません。
受講について
ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください)
アーカイブ配信 ►受講方法・視聴環境確認(申込み前に必ずご確認ください)
配布資料
- PDFテキスト(印刷可・編集不可)
受講料
77,000円(税込)/人