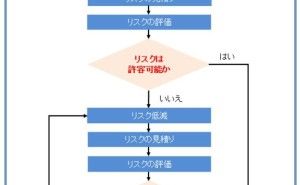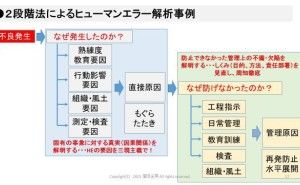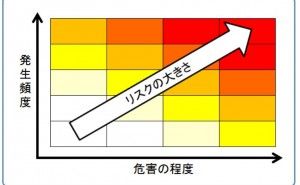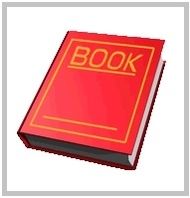▼さらに深く学ぶなら!
「安全工学」に関するセミナーはこちら!
先日、ある作業場で、先輩が新人に「解った返事をしようか。」や「もっと、大きな声で返事してみようか。」と話しているシーンを見かけました。その先輩曰く「なんか、恥ずかしがって大きな声を出さないんですよね~」と。返事は、話しの進め方、話す早さ、話す内容など、様々な調整をすることがで、情報の一方通行を改善することが可能です。また、安全意識を高めることができます。でも「なかなか返事をしてくれない」や「声が小さくて聞こえない」などの悩みを抱えるリーダーも少なくありません。私も、同じような悩みを抱えた過去があります。
重量物の搬送や運搬を行う工場現場では、作業員同士の声かけやかけ声が、作業の安全性や効率性を大きく左右します。しかし、多くの現場で、声を出すことに対して、恥ずかしさを感じてしまう作業員もいるのが現実です。今回は、声かけの重要性を、心理学やNLP(神経言語プログラミング)注.を通じて深掘りし、管理職や工場長が、どのように現場改善を進められるかを提案します。
1. 声かけ=恥ずかしいのメカニズム
なぜ「声かけ」を恥ずかしいと感じるのか?まず、作業員が声を出すことに抵抗を感じる、主な理由について見てみましょう。
社会的評価の恐怖
人は他者からどう評価されるかを常に意識します。特に「大声を出す」といった行為は、周囲の注意を引きがちで、普段とは異なる行動が求められるため、失敗を恐れて控えめになることが多いです。
内的対話と自己批判
NLP(神経言語プログラミング)によれば、私たちは常に自分自身と心の中で対話しています。声を出す行動への恐れが自己批判となり、「恥ずかしい」「変に思われるかも」といった、否定的な対話が行われてしまうことがあります。
メタプログラムによる動機の違い
人には、リスクを避けることに重点を置く回避志向と、目標達成を重視する達成志...