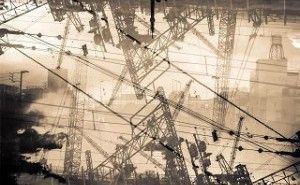専門家「浪江 一公」のキーワード解説
普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その2)
今回は、「イノベーティブな組織を強く求める」について解説します。 ◆関連解説『事業戦略とは』 1...
今回は、「イノベーティブな組織を強く求める」について解説します。 ◆関連解説『事業戦略とは』 1...
普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その1)
1. 曖昧なイノベーションの定義 近年において、イノベーションという言葉ほど頻繁に利用される言葉はないように思えま...
1. 曖昧なイノベーションの定義 近年において、イノベーションという言葉ほど頻繁に利用される言葉はないように思えま...
未来志向で見直す自社の強み 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その24)
前回は、オープンイノベーションを成功させるために、自社の強みの設定が必要であることを解説しました。今回は、その自社の...
前回は、オープンイノベーションを成功させるために、自社の強みの設定が必要であることを解説しました。今回は、その自社の...
自社の強みとは 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その23)
前回は、オープンイノベーションを成功させるためのビジネスモデルの必要性を解説しました。今回は、自社の強みの設定について議論したいと思...
前回は、オープンイノベーションを成功させるためのビジネスモデルの必要性を解説しました。今回は、自社の強みの設定について議論したいと思...
ビジネスモデルの欠落 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その22)
オープンイノベーションに取り組む日本企業に欠けている重大な問題に、『ビジネスモデルの欠落』があります。今回はこのテーマについて解...
オープンイノベーションに取り組む日本企業に欠けている重大な問題に、『ビジネスモデルの欠落』があります。今回はこのテーマについて解...
研究者自身が感じる脅威とは 『価値づくり』の研究開発マネジメント (その21)
今回は、オープンイノベーションに抵抗する心理として、研究者自身の能力の外部による置換の脅威について解説します。 ◆関連解説『事...
今回は、オープンイノベーションに抵抗する心理として、研究者自身の能力の外部による置換の脅威について解説します。 ◆関連解説『事...
『価値づくり』の研究開発マネジメント (その20)
今回はオープンイノベーションに抵抗する心理として、NIH(Not Invented Here)シンドロームについて解説します。 ...
今回はオープンイノベーションに抵抗する心理として、NIH(Not Invented Here)シンドロームについて解説します。 ...
『価値づくり』の研究開発マネジメント (その19)
研究開発担当者のオープンイノベーションへの抵抗の要因として、前回のその18で解説した「組織のホメオスタシス」の他に...
研究開発担当者のオープンイノベーションへの抵抗の要因として、前回のその18で解説した「組織のホメオスタシス」の他に...
『価値づくり』の研究開発マネジメント (その18)
前回のオープンイノベーションの心理学では、組織の構成員の持つオープンイノベーションに対する漠然とした不安について解説しま...
前回のオープンイノベーションの心理学では、組織の構成員の持つオープンイノベーションに対する漠然とした不安について解説しま...
『価値づくり』の研究開発マネジメント (その17)
前回まで、オープンイノベーションの経済学について解説しました。今回からは、オープンイノベーションの心理学について、解説します。 ◆...
前回まで、オープンイノベーションの経済学について解説しました。今回からは、オープンイノベーションの心理学について、解説します。 ◆...
『価値づくり』の研究開発マネジメント (その16)
今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の7つ目、「取引コスト」です。「取引コスト」は、これまでオープンイノベーシ...
今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の7つ目、「取引コスト」です。「取引コスト」は、これまでオープンイノベーシ...
『価値づくり』の研究開発マネジメント (その15)
今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の6つ目、「オープンイノベーションによる不確実性への対処」です...
今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の6つ目、「オープンイノベーションによる不確実性への対処」です...