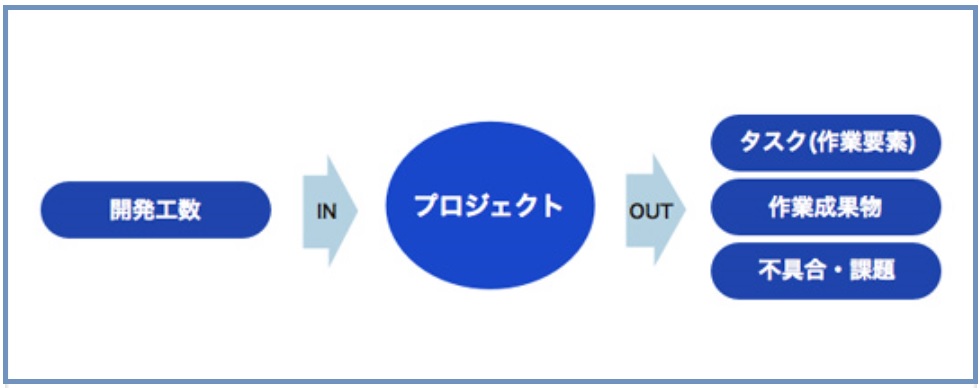
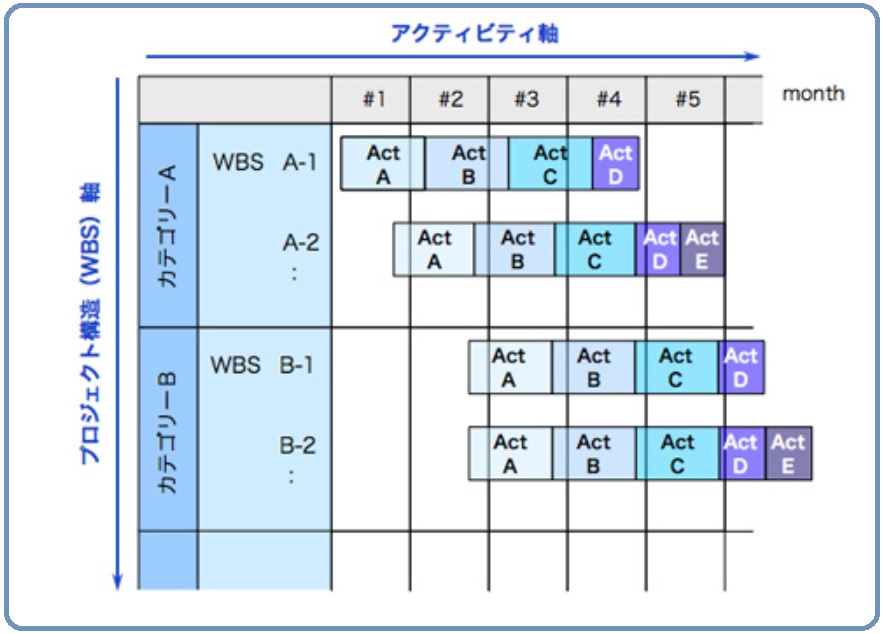
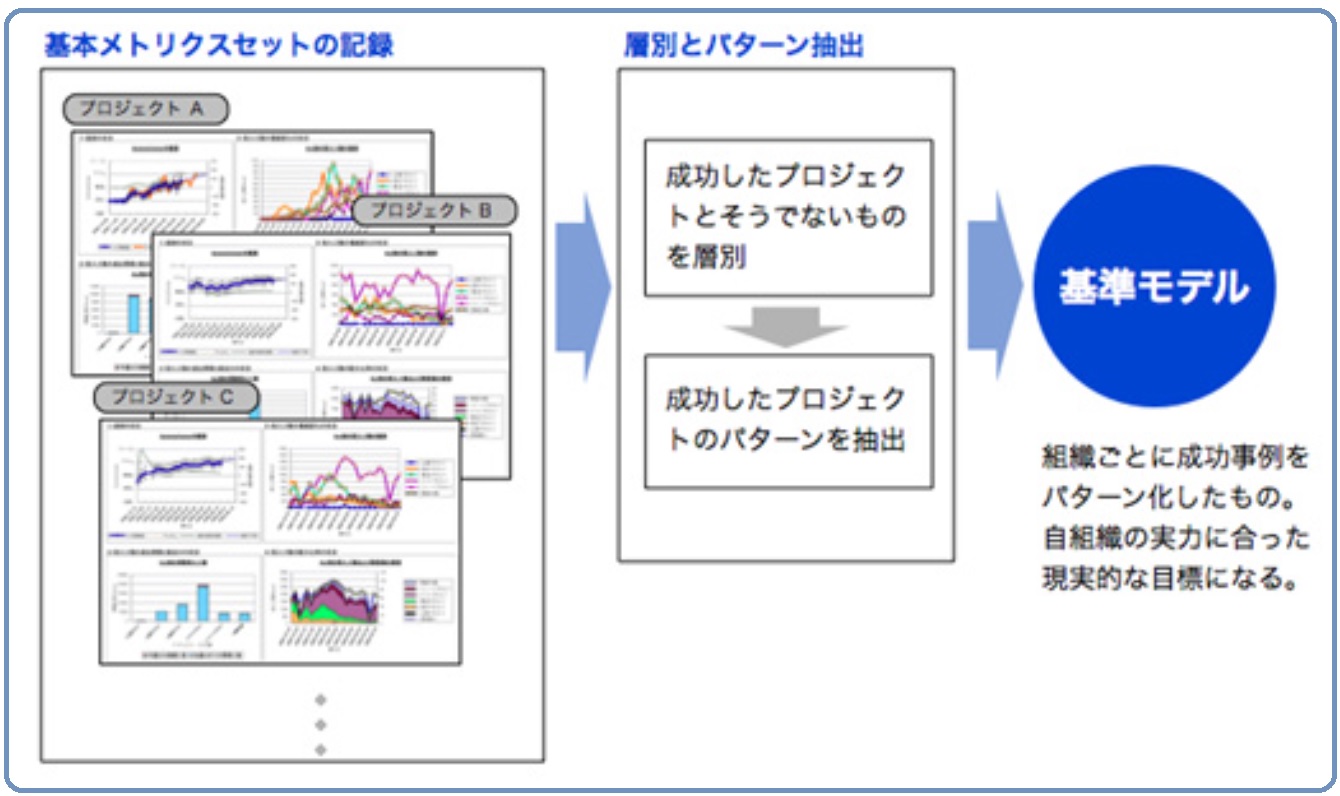
TOP

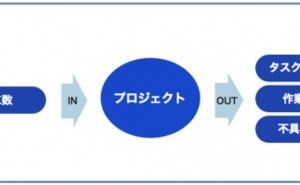
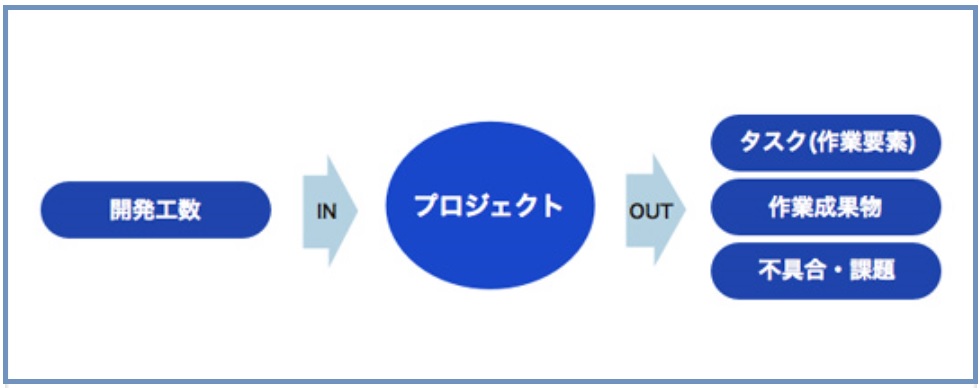
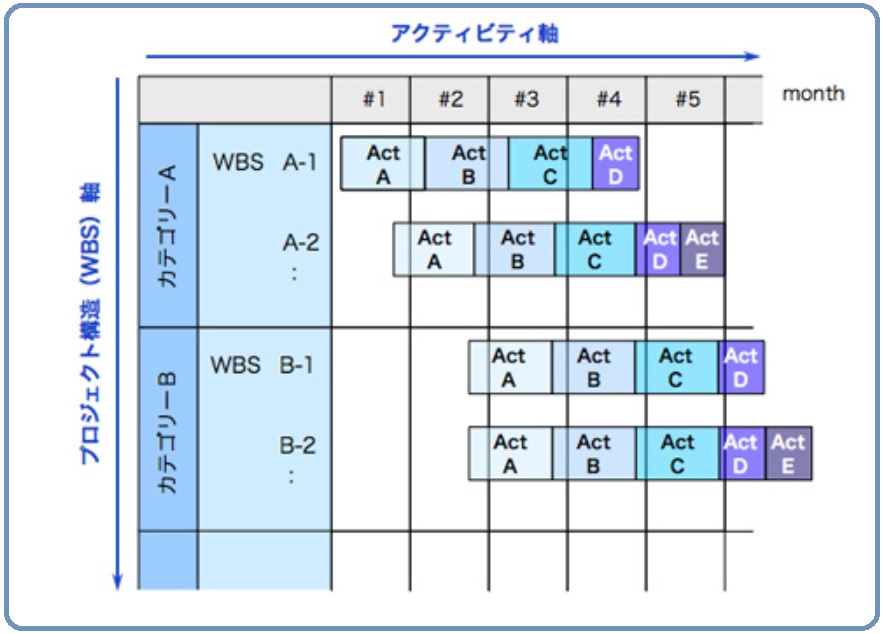
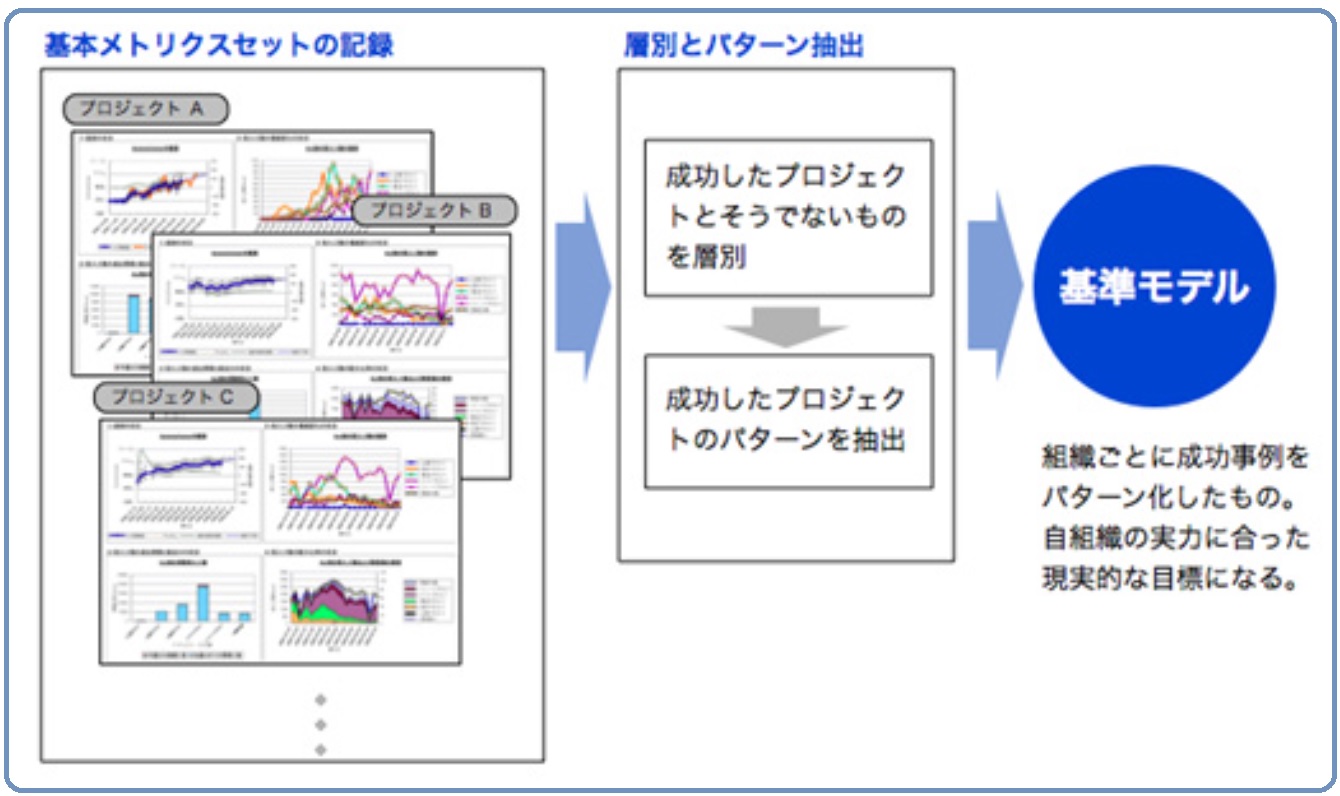
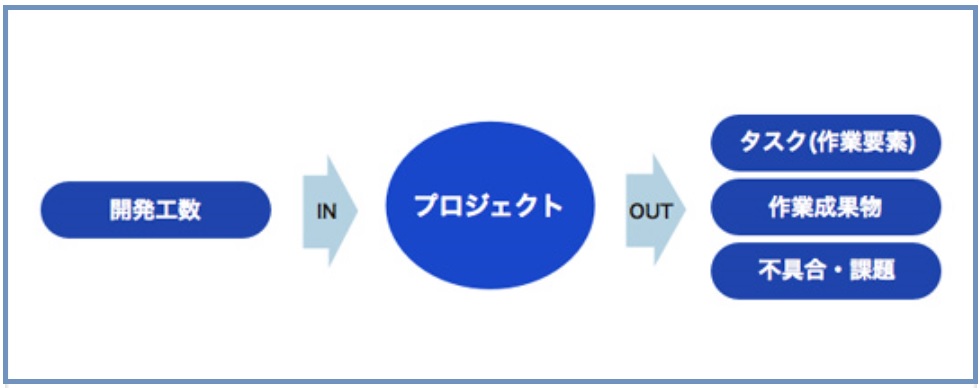
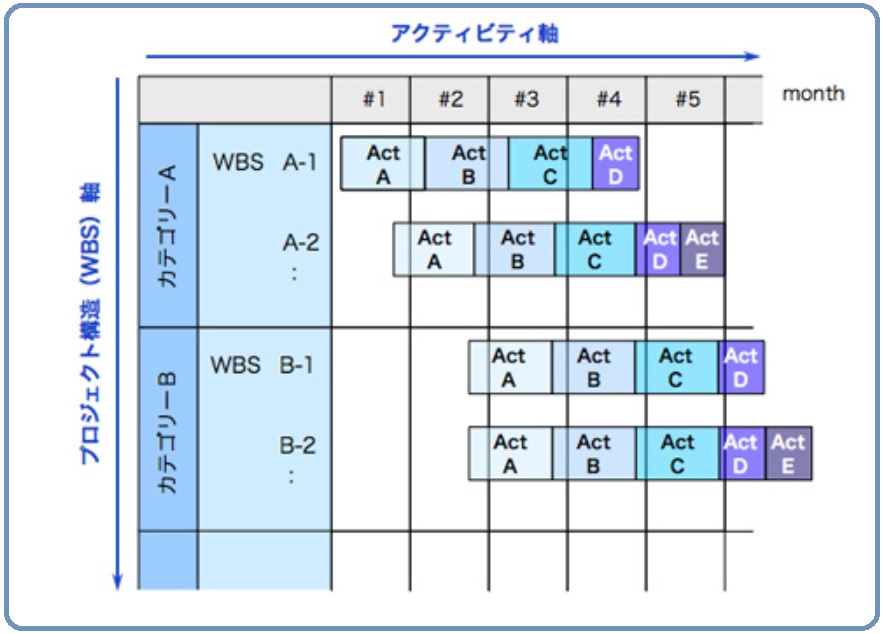
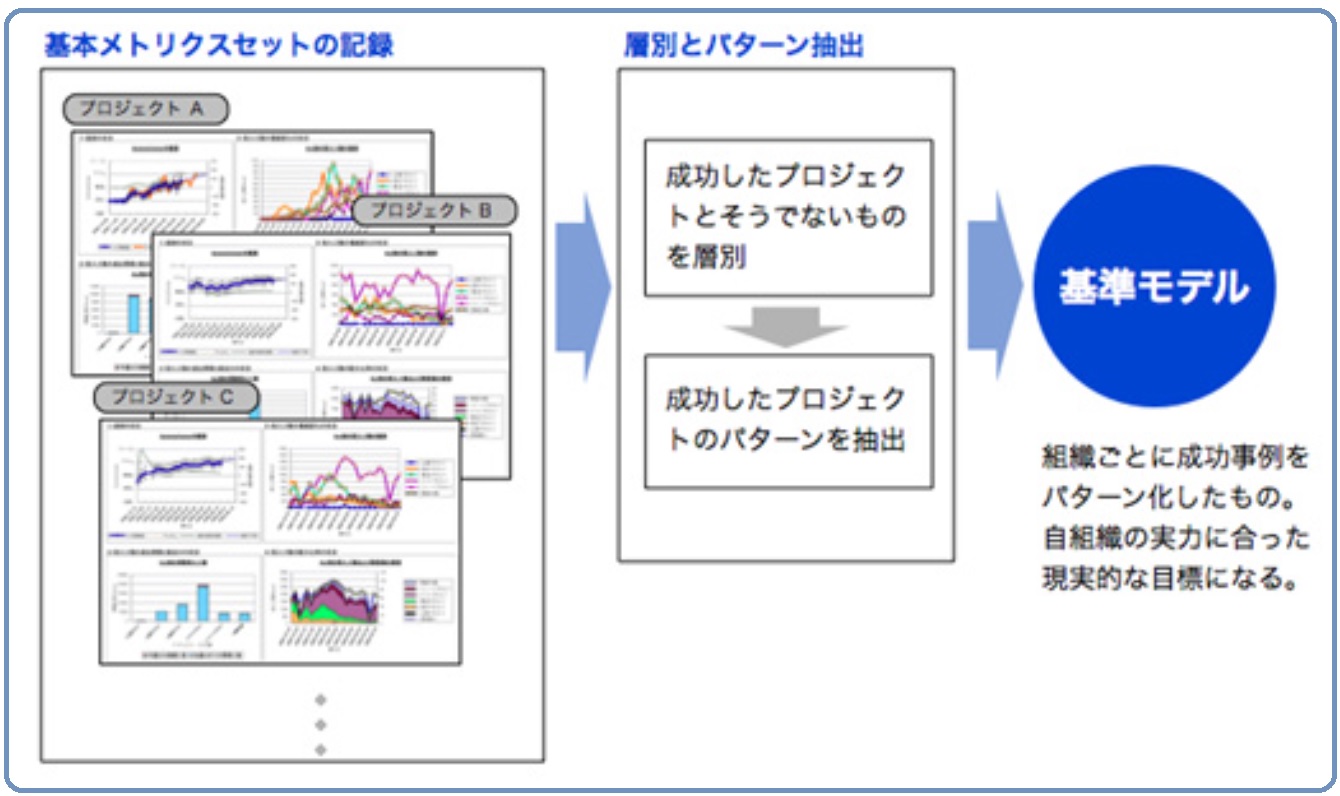
続きを読むには・・・
石橋 良造
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
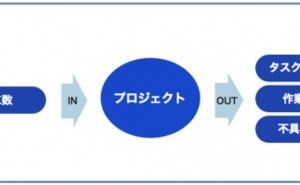
現在記事
一般的に、いくら投資して、どのくらい利益が出たのかを表す指標は、ROI=リターン/コストの式で表され、それらを費用対効果や投資効果と表現しています。公共...
一般的に、いくら投資して、どのくらい利益が出たのかを表す指標は、ROI=リターン/コストの式で表され、それらを費用対効果や投資効果と表現しています。公共...
今回は新規事業・新商品を生み出すためタネとなる「開発テーマ」の設定プロセスについて解説します...
今回は新規事業・新商品を生み出すためタネとなる「開発テーマ」の設定プロセスについて解説します...
・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め...
・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め...
1.機械の操作性の改善 自社の機械を購入してくれた顧客を訪問し、操作性について苦情を聞くことを中心に営業活動をしている機械メ-カがあります。多品種...
1.機械の操作性の改善 自社の機械を購入してくれた顧客を訪問し、操作性について苦情を聞くことを中心に営業活動をしている機械メ-カがあります。多品種...
【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きず...
【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きず...
前回からの続きです。前回ではまず製品開発工程の価値(物と情報)の流れ図を作り、工程上の問題点...
前回からの続きです。前回ではまず製品開発工程の価値(物と情報)の流れ図を作り、工程上の問題点...
開催日: 2025-04-18
開催日: 2025-06-17
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします


