(2) 要件に対するコミットメントを獲得する
(3) 要件変更を管理する
(4) 要件に対する双方向の追跡可能性を維持する
(5) プロジェクト作業と要件の間の不整合を特定する
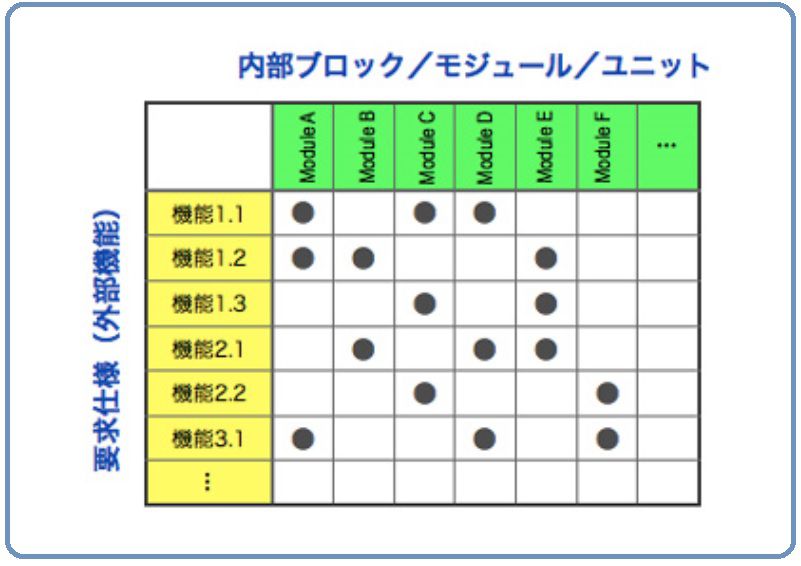
TOP


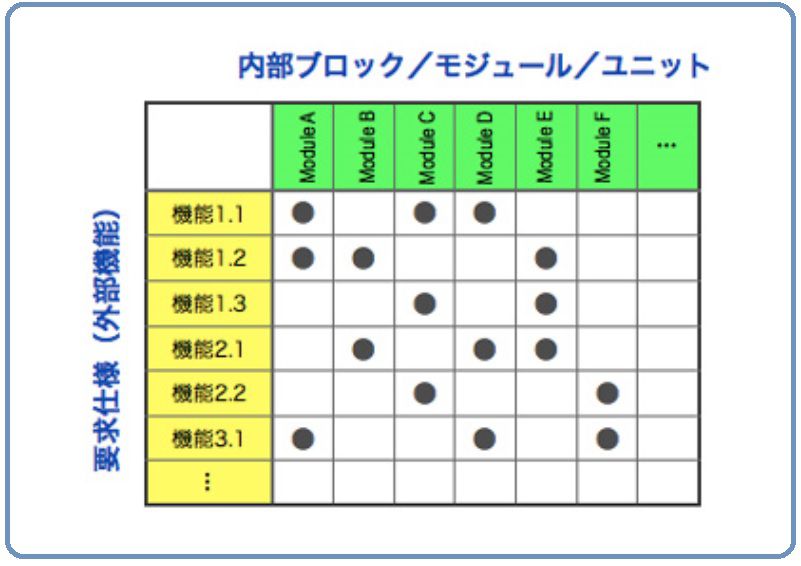
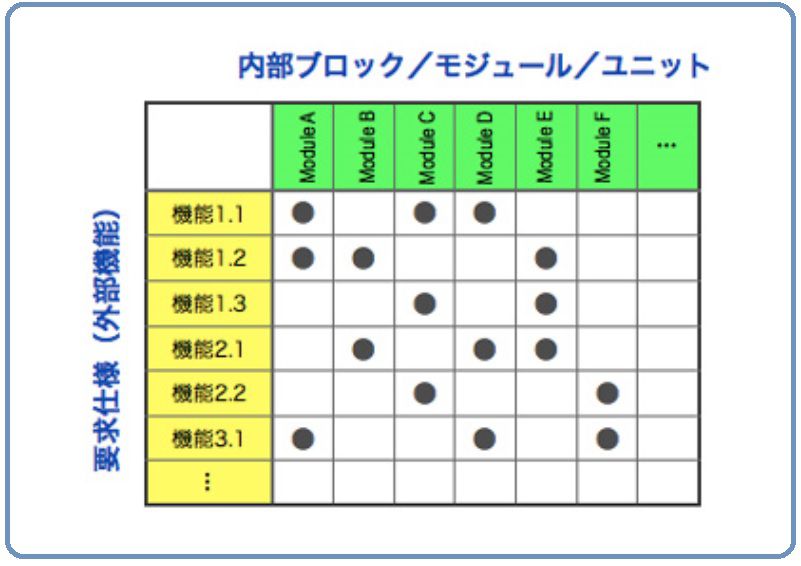
続きを読むには・・・
石橋 良造
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術者倫理」に関するオンデマンドセミナーはこちら! 1. はじめに 前回の「新入社...
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術者倫理」に関するオンデマンドセミナーはこちら! 1. はじめに 前回の「新入社...
前回の「リーン製品開発※の全体像 – イベント駆動型のプロセス」に続けて解説します。 ◆ 統合プロダクトチ...
前回の「リーン製品開発※の全体像 – イベント駆動型のプロセス」に続けて解説します。 ◆ 統合プロダクトチ...
◆ 研究開発にMVPを活用する 今回は「研究開発にMVPを活用する」をテーマに解説します。 MVPとは、Minimum Via...
◆ 研究開発にMVPを活用する 今回は「研究開発にMVPを活用する」をテーマに解説します。 MVPとは、Minimum Via...
前回のその1に続いて解説します。それでは、まず「調整」の仕組みについて考えたいと思います。最初に質問です。調整の仕組みが欠如した製品開発はどのような状態...
前回のその1に続いて解説します。それでは、まず「調整」の仕組みについて考えたいと思います。最初に質問です。調整の仕組みが欠如した製品開発はどのような状態...
今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU...
今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU...
◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての...
◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての...
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



