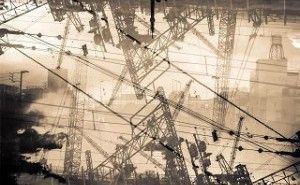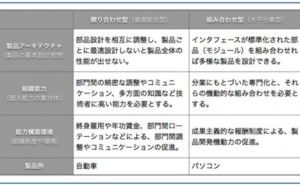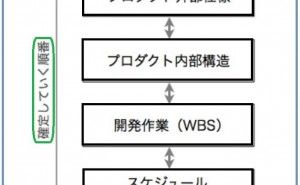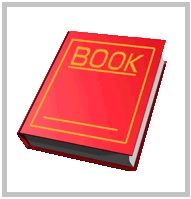『価値づくり』の研究開発マネジメント (その2)


1.「効率的」に「多様」な活動を行う
2.企業の知見・経験を利用できる分野で活動をする
3.対象分野を「目いっぱい広げる」
4.「効率的」に「多様性」を求める分野:市場と技術
5.日本の製造業の大きな問題:視野狭窄
6.自社の市場と技術を目いっぱい広く、遠く見る
続きを読むには・・・
この連載の他の記事

現在記事
「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事
もっと見る『業界初のテーマ』を簡単に認めても良いのか?~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その40)
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に...
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に...
日本の事例 オープンイノベーションとは(その4)
【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...
【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...
普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その174)イノベーション創出
【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その173)へのリンク】 前回まで自分が生物...
【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その173)へのリンク】 前回まで自分が生物...
「技術マネジメント総合」の活用事例
もっと見る‐顧客の難しい要求に取り組む ‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その2)
前回の事例その1に続いて解説します。顧客から難しい要求や相談があったとき、意欲的にその問題に取り組む企業がある。その取組みから他社では出来ないよ...
前回の事例その1に続いて解説します。顧客から難しい要求や相談があったとき、意欲的にその問題に取り組む企業がある。その取組みから他社では出来ないよ...
擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その1)
【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を...
【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を...
進捗管理可能なソフト開発計画 プロジェクト管理の仕組み (その6)
前回のその5:ソフト開発計画の作成方法に続いて解説します。 製品機能に対するソフトウェアの各モジュールが実装すべき処理(内部機能)が...
前回のその5:ソフト開発計画の作成方法に続いて解説します。 製品機能に対するソフトウェアの各モジュールが実装すべき処理(内部機能)が...