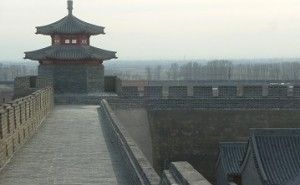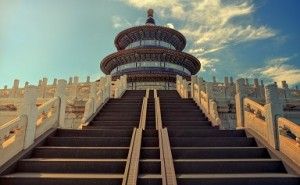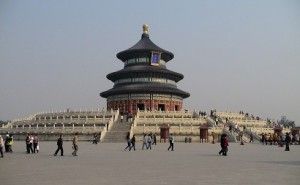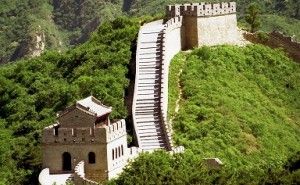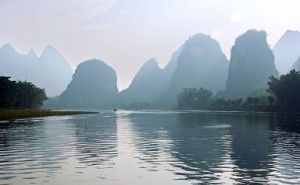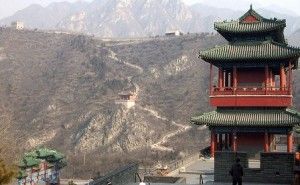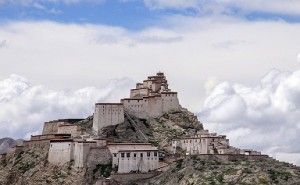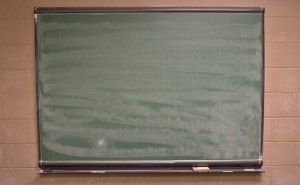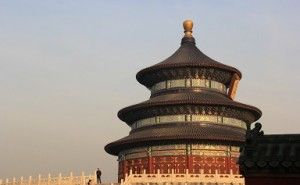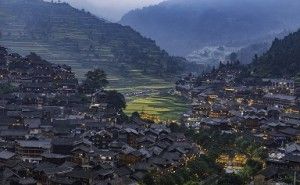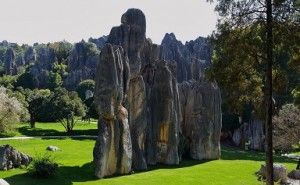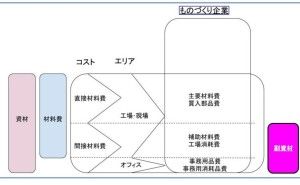前回のその69に続いて解説します。
【第4章】中国新規取引先選定のポイント
◆ 契約書取り交わしのポイント
ここでは取引先と取り交わす仕様書について、中国企業と取り交わす際のポイントを取り上げます。
(1)あいまいな表現は厳禁
あいまいな表現は誤解の原因となります。スペックや良品・不良品の基準は明確にすることが大事です。要するに、誰が見ても違う解釈とならないようにすることです。判断の基準が明確となる表現にすることが必須です。判断が主観に依らないようにしなければなりません。特に良・不良を決める検査基準、その中でも外観基準はあいまいになることが多いので要注意です。
例えば、外観基準を表す言葉が「有害な傷がないこと」となっていた場合。
この表現は問題があります。どこが問題だと思いますか?
「有害な」という部分が問題です。何を持って有害とするかが明確ではありません。
では、表現を「傷なきこと」と変更したら、どうでしょうか。実はこれでもまだ問題があります。どのレベルで見るかが問題です。肉眼で見て傷が見えなければよいのか、拡大鏡で見るのか、それとも顕微鏡で見ての判断なのかを明確にしなければなりません。
(2)当たり前のことも明文化
日本では当たり前のことや常識的なことはわざわざ書かない、明文化しないことも多いですが、中国企業との取り引きではそれらも明文化する必要があります。それは何度も言っていますが、日本と中国では当たり前や常識が異なるからです。特に外観検査基準は、日本では誰が見ても不良というものでも基準として明文化することが絶対です。
外観に関する感性の違いは大きいです。以前筆者のセミナーに来た方から「中国企業と自社とで検査基準が違う」という相談を受けました。基準を示して合せることをしていないのかな?と思っていたのですがよく聞くと「中国の取引先が外観検査を行っているが、どう見ても不良というものが納入されてくる。どうしたら良いでしょうか?」ということでした。その方に確認すると、どう見ても不良という項目については、当然不良と判断するはずなので、基準として取り上げていないということでした。
中国人と日本人は、外観不良に対する尺度が違うので、日本人が当たり前と判断するものでも中国人は不良と思わないことがあります。ですからこうした不良が出るたびに基準に追加して「次の検査では不良としてはじく作業をやる必要があります」と話をしたところ「そこまでやらないと駄目ですか」と言っていたので「やらないと駄目です」と答えました。逆にこのような事例もありました。外観検査基準は「傷がないこと」でした。しかし、日本の検査では顧客が使わない製品の外周部の傷については暗黙の了解で、傷があっても合格としていました。
しかし中国の検査では、外周部であっても傷があれば不合格にしていたので、不良率に大きな差が出る結果となりました。暗黙の了解という当人たちにしか分からない基準が中国側に伝わっていなかったのです。
また梱包に関しても、認識の違いから起こるトラブルも少なくないので、梱包仕様もしっかり確認しましょう。中国では、製品が保護されていれば少々見栄えが悪くても構わないと考えていますが、日本では梱包の見栄えも品質の内と考えています。こちら側の要求をしっかり伝えましょう。
(3)重要ポイントを明記
第4章の最初で書いたように、これは日本企業との間でも起きる問題だと思います。使う側(買う側)が重要...