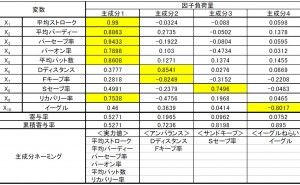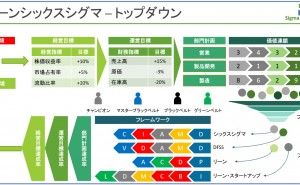前回の【快年童子の豆鉄砲】(その120)QCサークル活動スパイラルアップ戦略(7)からの続きです。
【QCサークル活動スパイラルアップ戦略の進め方】
3. 1ラウンド(1R:半自主活動)の進め方
1)はじめに
1Rスタートの前提として、リーダーを通じた職制の全面支援を受けた0R活動でサークルに芽生えた「スパイラルアップ力」の存在がありますので、その点を再確認しておきたいと思います。ここでいう「スパイラルアップ力」とは、一つの目標を達成できた達成感が次のより高い目標への挑戦意欲を生む力のことで、これが繰り返されることにより成長を続ける様を“スパイラルアップ”と言う言葉に込めています。
要するに、1Rスタートには、この「スパイラルアップ力」を生む達成感が必要なのですが、最初ですので、達成感で終わってしまうこともあり得ますので、そうならないためには、0Rの活動成果に対する職制や他サークルからの積極的な評価表現、いわゆる誉め言葉が有効ですので、念頭に置いて頂ければと思います。
2)目標の設定
0Rの活動状況で把握したサークルの実力に見合った少し高めの目標をリーダーと相談しながら設定するのですが、その過程で、活動に見合ったふさわしい目標設定の仕方をリーダーに伝授し、2R以降の目標設定を任せられるようにするのがポイントです。
3)QCストーリーの立案
目標達成のための活動計画に相当するものですが、今回は、作業分担を含め、リーダーが作成したものに対してアドバイスを与えるという形をとるのが基本ですが、次項でご説明するQC手法の紹介による活動のレベルアップが最大のポイントになります。
4)QC手法の活用
0Rは職制による“全面支援”が原則でしたが、1Rは“半自主活動”、即ち、職制としては、リーダーが相談に来ない限り様子を見るスタイルでいいのですが、この“QC手法の活用”は、リーダーがマスターできるよう“全面支援”が原則です。
5)自主活動意識の醸成
このラウンドのポイントは、目標達成した際、リーダーを含めて「QC手法の活用以外は俺たちがやった」と言う意識を持ってもらえることで、今後の活動の自主性向上につなげるところにありますので、支援についてはその点を意識願います。
6)自主活動体制への移行の可能性確認
職制にとって、担当サークルが1Rを終了し、2Rへの移行、即ち、自主活動体制への移行の可能性が確認できるのは「サークル活動を通じて自分たちの力で職場がよくなることを実感」しているだけでなく「活動をもっと自分たちの力でやりたい」即ち「活動の自主性」を求めているかどうかです。
その確認のために、リーダーに対し「君たちのサークルは“自主活動体制”の力が付いたので、今度の目標については自分たち自身で取り組んでみてくれないか」と自主活動を促し「勿論、困った時や確認したいときは何時でも言ってきてくれ」と、支援体制を受け身にするステップを設け、この間の支援要請内容、並びに活動状況の観察結果によって、1Rの終了と2Rへの移行をサークルに宣言するのがいいと思います。
4.2ラウンド(2R:自主活動)の進め方
1)はじめに
2Rスタートの前提として、サークルに自主活動体制能力が備わっている、即ち、職制の全面支援を受けて進めた1Rの活動ステップを自分たちで進めることができることが挙げられ、職制はサークルの目標達成活動を見守ればよいということになります。
...