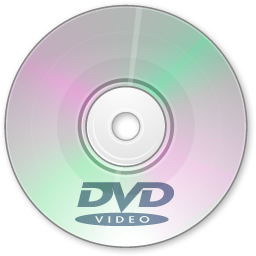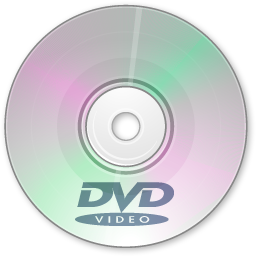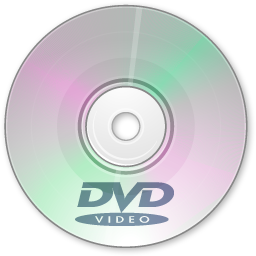◆ポールスター(北極星)
理念経営体系の社員満足の展開の話の最中に“ポールスター(北極星)”が出てきて戸惑われたと思いますが、次弾以降に出てくる重要なキーワードですので今回、(その17)としてご説明させて頂く次第です。
【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その16)理念経営体系の設計(5)へのリンク】
企業人は、目標に向かって一生懸命、時にはがむしゃらに頑張るものだと思うのですが、取り組む目標は、筆者の中では二通りあると思っています。
一つは、挑戦要素は含まれてはいるものの、ある程度到達のための道筋が見えている数値目標で、この場合は、周辺の状況や環境の変化に応じて調整がなされる一般的に“目標”と言われているものです。もう一つは、その先にある、志の高い、思いのこもったもので、こちらの場合は、周辺状況や環境の変化に影響されることの無い不動の目標と言え、一般的には“夢”と言われているものに当たると思うのですが、筆者は、あくまで“目標”と言う意識でいます。
この二つは、明確に区分して、その違いを意識して取り組む必要がありますので、筆者なりに納得の行く命名を色々探したのですが、うまい日本語が見つからず、特に後者に対する命名に苦労しました。そこで思いついたのが、“ポールスター”だったのです。
これは、入社間もないころ、英語の勉強をしていたとき、polestarの訳に、北極星以外に、「昔の船乗りが航海の道標にした天空の不動の星」の意を受けて“指標、目標”と言う訳があることを知り、とても印象に残っていたのですが、この“不動”と言う言葉が、後者の目標にぴったりだと思ったのです。
そこで、後者が、英語の“ポールスター”なら、前者も英語の“ターゲット”にすることにしたのです。それ以降、会社から与えられたり、自分自身で建てた実務上の目標“ターゲット”に取り組むときには、必ず、その延長線上に“ポールスター”を設定して取り組んできたのです。
そのおかげで、高い成果を手にすることが出来ただけでなく、オリジナリティの高い達成プロセスの開発に繋がり、ここにこうしていろいろご紹介できているわけです。因みに、理念経営基本体系展開上での、企業の存在価値を決める3要因、社員満足(ES)、社会満足(SS)、顧客満足(CS)に取り組む際のそれぞれに対する筆者なりの“ポールスター”を、次に記述しますので、ポールスターのイメージ把握の参考にして頂ければと思います。
- ESポールスター:最適材・最適所における自己実現と尊敬欲求の充足
- SSポールスター:女性・高齢者・非健常者が生き生きと力を発揮し、地域の子供たちが憧れる企業
- CSポールスター:末端ユーザーに夢と感動を与え、顧客感動に繋がる商品の開発
今ご説明している理念経営基本体系は、中小企業が抱える17の課題のトップに上げた「経営理念が浸透しない」に対する解決策なのですが、この“ポールスター”は、その重要な要素と言えるのです。
“経営理念”は、企業経営活動を展開する上での指針となる基本的な考え方、哲学、信念で、それをもう少し具体的に企業が目指す姿として“ビジョン”が示されるのですが、双方とも、社員の日常の仕事とはかけ離れているのが通常で、社員にとっては今一つピンと来ないと言うか、日常の仕事との関わりが認識できないのが現実ではないかと思うのです。
その点、“ポールスター”は、ここに示された三つのポールスターを見て頂くと分かるのですが、企業にとって重要な課題それぞれに対して、かなり具体的な内容が示されていますので、日常の仕事に与えられた数値目標との関連をかなりのレベルで意識することが可能になると思うのです。
“ポールスター”は、経営理念の展開過程で示されるものですので、結果として経営理念が日常の仕事に生かされ、浸透することに繋がると言えるのです。要するに、日常業務に密着している“ターゲット”を、今までかけ離れた存在であった“経営理念”や“ビジョン”と結びつける橋渡し役を“ポールスター”が果たしてくれるのです。
このように、経営理念を、理念経営基本体系を通して、重要な経営課題ごとに“ポールスター”を設けることにより、経営理念を社員の日常業務に浸透させる経営を“ポールスター経営”と呼んでいるのですが、お勧めしたいと思います。
因みに、このポールスターを念頭に置くようになって以降、筆者の中だけの話なのですが、“ターゲット”しか頭にない人たちを“ターゲット族”、“ポールスター”を持って仕事に取り組んでいる人たちを“ポールスター族”と呼ぶことにして周囲を観てきましたが、残念ながら、“ポールスター族”に出会うことはありませんでした。(ポールスターを内に秘めた方がおられたかもしれませんが…。)これを...