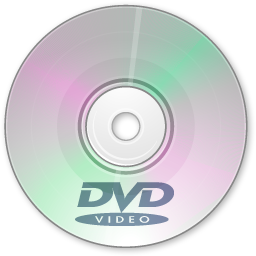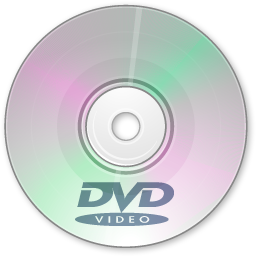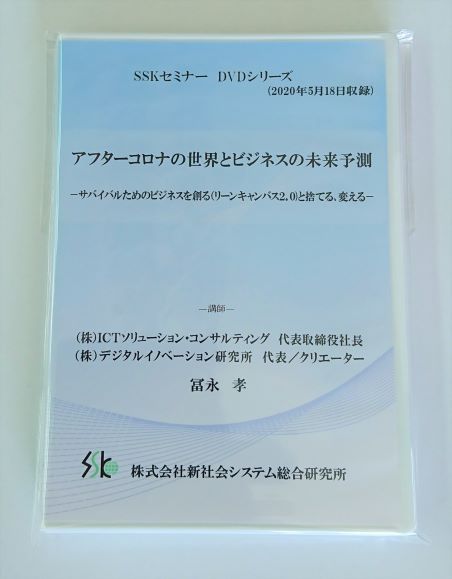◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!
◆自社の真のコア・コンピタンス把握事例(1)
1.事例の背景
ある自動車部品メーカーの品質経営のお手伝いをすることになり、5年契約での就任早々の社長さんからお話を伺ったところ、会社の実情把握のために、就任3か月前から顧問として毎日開催されるトップマネジメント会議をはじめとして諸活動に参画する機会があり、そのお陰で、その企業が抱えている問題点や弱点がかなり明確に把握できたので、それらの情報を、経営戦略の立案、遂行に生かして行きたいとのことでした。
お話の内容は素晴らしいものだったのですが、前弾でご説明した21世紀の経営に求められているところをご説明した上で、経営戦略立案の起点を「自社の“真のコア・コンピタンス”の把握」にされることをお勧めしたところ、全面的な賛同を得て実現した事例です。
【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その24)へのリンク】
2.適用手法
メーンに使う手法は“連関図法”ですが、補助手段として“親和図法”を活用しました。
3.テーマの選定
解析に必要な言語データを採取するためには、真のコア・コンピタンスを引き出せるような“テーマの質”が勝負になりますので、「御社の、他企業にはおいそれとまねのできない点」を上げて頂くよう、トップマネジメントの方にお願いしたところ、選定されてきたテーマ名は、企業業績に直結する素晴らしい次のようなものでした。
「経営環境が激しく変化する中で当社が15年間黒字を継続できているのはなぜか?」
4.言語データの採取
・データ採取対象:全部門の係長以上
対象は、全部門で、少なくとも係長以上が必須になります。と言いますのは、企業活動の最前線の状況を把握できているのは係長ですので、課長以上ですと、採取データが観念的になるきらいがあり、「真のコア・コンピタンス」の把握に至らない心配があるからです。
・データ採取方法:アンケート方式
対象者を係長以上にしますと、この会社の場合80人を超えますので、一堂に会したブレーンストーミング(BS)は物理的に無理があるだけでなく、各人が感じているところを素直に出せる環境にはならないのと、この場合、BSの重要な利点である“相互啓発”に期待する面が余りありませんので、アンケート方式がふさわしいと言えます。
・採取データ数:219(57人)
必ずしも身近なテーマではないにもかかわらず、活発な意見データを多くの人から手に入れることが出来たのですが、プロジェクトチームの人たちにヒアリングしたところ、自分たちのいい点に着目したアンケートは初めてだったので、高揚感をもって抽出することが出来たからだと思う、とのことで、コア・コンピタンス把握の効用の一つではないかと思いました。
5.解析手順と結論
Step 1:親和図法によるカード寄せ:219 → 40
データ採取がアンケート方式でしたので、よく似たデータが多数みられましたので、それらのデータの処理を「親和図法のカード寄せ」、即ち、単なる分類ではなく、各データの思いをくみ取り、時には、その背景に潜む思いも汲み取った“表札カード”を作り上げる作業を行った結果、219あったのが、最終的に40に集約することが出来ました。
データ数がほぼ五分の一になりましたので、ネグレクトされたデータがあるのではないかとの懸念を持たれるかと思いますが、関係者の印象は逆で、うまく表現できていなかった点が上手な表現になっており、データとしてはむしろ質が向上したという印象がある、とのことでした。
これは、親和図法のカード寄せ機能の効用のなせる業で、このステップは成功だったと言えます。
Step 2:連関図法による解析:メーンカード5つ
219を親和図法で絞り込んだ40の言語データを、連関図法で解析した結果、熟成度指数(注)k=1.85になった時点で、下記のような、結論に直結するメーンカード5つを手に入れることができました。
- ①管販・利益率が他社に比べてよい
- ②顧客との信頼関係により受注できている
- ③原価管理システムが強力かつ継続的に全社で行われている
- ④リスクミニマム方針をベースに堅実経営をしてきた
- ⑤従業員の会社に対する忠誠心が強い
(注) 連関図法は、入手した言語データ相互の因果関...