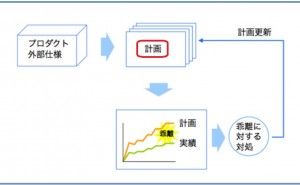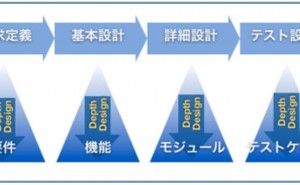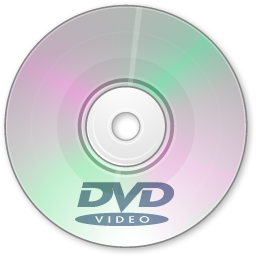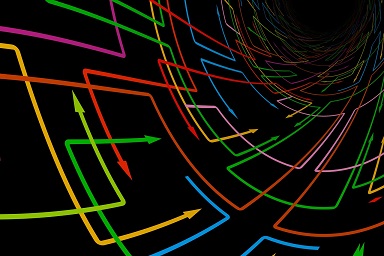
今回は、現在の「イノベーションを起こすためには」の解説から、ちょっと逸脱して、「イノベーションとは」の再考をしてみたいと思います。
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その138)へのリンク】
以下は、普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その138)イノベーションの創造からの引用です。
「ちょっと脱線しますが、大げさに聞こえるかもしれませんが、私は日本企業、ひいては日本経済の低迷の元凶はここにあると思っています。目の前にある確実なもの、実績のあるものにひたすらしがみつき、何とか事態(企業業績や日本経済の低迷)の好転をはかろうとする。このアプローチには一見なんの問題もないように思えるかもしれませんが、アジアの新興国企業が力をつけた中で、「確実なもの、実績のあるもの」ではこれら企業と泥沼の競争になるということがあるということです。」
その後、日本経済新聞の2022年10月26日の夕刊の「プロムナード」の中で、京都大学の教授である藤原辰史氏の「人文書とイノベーション」を読み、その考えを強くしました。藤原教授はこの記事の中で少し長いのですが、引用すると以下を書いています。
「食にせよ、道具にせよ人間にはものを独占する喜びよりも共有する喜びの方が長続きするというのが私の考えだが、そんな反個人主義的な商品を作ってみたいという人が意外と多いのである。あるいは、企業は生産をやめ、消費者も消費をやめ、「分解」世界から世界を立て直す、と言うのが私の『分解の哲学』の主張だが、こんな反時代的かつ社会批判の本を読んで、経営に活かし、成長を続けている企業経営者も複数いる。・・・話に来る若手の多くは、企業の上層部が、そもそも社会そのものへの批判力が低下している以上、新しいアイデアが生まれにくい、と冷静に判断している。そんな企業風土に抗いアイデアを仲間と練り出すために若手社員が通勤時間に手に取るのは・・・哲学や歴史や文学などの、批判力をその生命とする人文書であり、その社会をラディカルに問い直すアイデアがイノベーションを起こしている」
ということで、イノベーションの定義を問い直す必要がある、と強く感じています。
私はこれまでも何度か解説議論していますが、イノベーションとは「今まで存在していなかった大きな顧客価値を実現すること」と定義しています。その理由は、自社の収益を最大化するためには、競争がない中(←「今まで存在していなかった」)で、大きな顧客にとっての価値(「大きな顧客価値」)を実現することが必要であると考えたからです。この中の顧客価値を広く捉えようと、顧客価値拡大モデル:VACESなどというというモデルを提示してきました。
しかし、それをもっと拡大して「社会価値」の拡大と明確に定義すべきではないか、と考えはじめています。もちろん、マイケル・ポーターはすでに随分前からCSV(Creating Shared Value)経営を提唱し、日本企業の中にも、キリンのようにCSV経営を標榜している企業は既に存在していますので、後追いと言えば後追いなのですが。CSVとは社会に貢献しながら、同時に企業として収益機会を拡大するという概念です。
しかし、この社会価値の全体像については、まったくもって明確にはなっていないのですが、まさに明確になっていない社会価値の全体像を広くかつ深く考えてみることにより、新しい価値を社会...