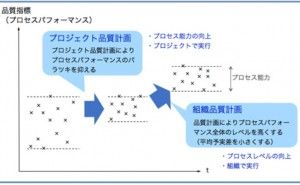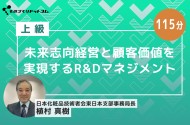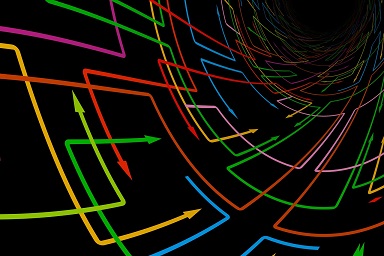
イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。
具体的には、ここまで考えてきた「踏み出すこと・踏み出そうとすることで発生する直接的コスト」×「心理的コスト」の内、心理的コスト(その2):エネルギーをセーブしたいと思う人間の基本心理が存在にどう対処するのが良いのかを考えていきたいと思います。
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その141)へのリンク】
1.イノベーションのための最初の一歩を踏み出すことを妨げる「めんどくささ」
人間はめんどくさがりです。人間のこのような特徴を善意に捉えると、そもそも太古から人間は、常に危険な環境に身を置き、危機に直面した時にその状況に即時に対応できるように、常に備えておかなければならない、ということがあるように思えます。そのため、危機のない状況にあるときには、エネルギーを温存し、危機に備えるということがあり、それが「めんどくさがる」ということとも理解できます。
2.「めんどくささ」を払拭する方法
人間が本来持つめんどくささを払拭し、行動を起こすにはどうしたら良いのでしょうか?それには、私は次の5つがあると思います。
- (1)仕事を細かく分割する
- (2)隣接可能性の効果を信じる
- (3)第一歩を踏み出したことを自分自身でほめる
- (4)時間を掛けても良いと考える
- (5)行動を重視する習慣・カルチャーを作る
では、前回、(1)(2)(3)(4)まで解説しましたので、今回は(4)の続きからですが、この時間を掛けても良いと思えるようにするための長期での目標設定について、解説をします。
(4)時間を掛けても良いと考えるの続き
◆イノベーションを駆り立てる長期の目標の要件:ワクワク
長期の目標の内容はいろいろであると思いますが、長期の目標は、持続してその目標に向かって毎日の思考や行動を駆り立てるようなものでなければなりません。そのような長期の目標は、一言で言うと「ワクワク」するものである必要があります。それでは「ワクワク」する目標とは、どのような要件を備えている必要がある必要があるのでしょうか?それらは、以下の3つの要件であると考えます。
・目標が達成されることは、自分、組織そして社会にとって真に大きな価値がある
高い目標の達成には、必ず自分達にとって重要な何かを相当なレベルで犠牲にしなければなりません。犠牲にするのは、安定的な地位、資産、時間、エネルギーなどです。そのため、その犠牲を払っても相当余りある価値を生み出すものがなければ、その目標に向かって自分の思考や行動を駆り立てることはできません。これは、ワクワク感を生み出す大前提となるものです。
しかし、その目標が自分が属する組織や社会に悪影響を及ぼすのであれば、ワクワク感は減殺される、もしくはそもそもワクワク感を感じることはできません。この点もワクワク感を生み出すポイントとして重要です。
・他人があまり設定しないようなユニークな目標
しかしこれだけでは、ワクワク感を生み出すには、頭ではわかっていても、腹の底から目標達成に駆り立てるというものにはならないのではないでしょうか。この点に関し、目標が他人から見て凡庸な目標であると、人間はワクワクしないものです。一方で、他人、他社が達成をあまり考えないようなユニークな内容の目標、もしくは他人、他社が考えないような高いレベルの目標であると、おおいにワクワクするものです。
米国のアポロ計画。1962年に当時の米国のケネディ大統領は、1960年代の内に有人月面着陸を達成するという目標をたてました。これにより米国の国民の士気は多いに高まり、1969年に公約通り、米国は人類にとって画期的な有人月面着陸に成功します。
なぜ他人、他社が設定しないような目標はワクワク感を生み出すのか?それは世の中での自分達の有能感や存在感を、多いに高めるからではないかと思います。世の中で、自分や自分達の有能感や存在感を高める効果には、極めて大きなものがあります。例えば、特攻隊の隊員は、自分の命を犠牲にしても、国を守る(現実には特攻で国を守ることはできないのですが)ことをするわけです。それは自分の命という究極の犠牲を払っても良いと思える程に、自分の有能感や存在感を、この特攻隊の例で言うと崇拝されるというレベルまで高めてくれるからです。
加えて、まだその目標が達成されていない段階か...