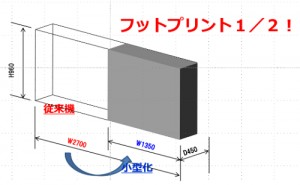前々回から時系列や物理量で整理した知識を、更にそれらの関係性を考え整理・拡大することについて解説をしています。今回は「原因と結果」の2つ目の類型の「ピラミッド(一つの原因→複数の結果)」についてです。
1. 1つの「結果」から芋蔓式に、他の「結果」を考える
これまで「風が吹けば桶屋が儲かる」を例に解説をしていますが「風が吹く」という原因は「土埃を舞い上げる」という一つの結論だけでなく「他の物を舞い上げ」たり、その他にも「物を変形」させたり「摩擦熱を生み出す」など、複数の結果を生み出すことができます。
ここで重要なことが一つでも「結果」として分かると、そこから芋蔓式に他の「結果」を想定することができるということです。
「土埃を舞い上げる」ことができるのなら「他の物も舞い上げる」ことができるだろう。風は「物を舞い上げる」だけなのか、といった思考・連想をすることができるからです。
2. 原因の本質を定義する:「風が吹く」とはどういうことなのか?
実はこの点は前回の「重要点」と同じなのですが「風が吹く」の本質は何かを考えて定義することに他の結果を想定することができます。
その本質の一つを言語化すると「空気という質量を持ったものが移動する」ということです。
そうであるなら土埃以外の物も舞い上げることもできますし、たとえ舞い上げることができなくても物を移動させることができるかもしれません。また対象物の形状によっては対象物周辺に圧力差を発生させ浮き上がらせることができたり(飛行機が飛ぶ原理です)、摩擦熱で対象物の温度を上昇させることもできるという結論を連想することができます。
3. 連想を生み出す源の知識・経験を多く持つ
他の結果を連想するためには、上の「原因の本質を定義する」こと以外に、もう一つ重要なことがあります。それは連想の源となる知識や経験を多く持つことです。知識や経験が多くあればある程、連想の可能性が高まります。
上の例を参考にすると、風で木の葉が舞い上がる状況を見ていれば「風は土埃だけを舞い上げる訳ではない」ことが分かりますし、風が強い日は洗濯物が乾きやすいという経験をしていれば「風は水分を吹飛ばしてくれる(現実に...